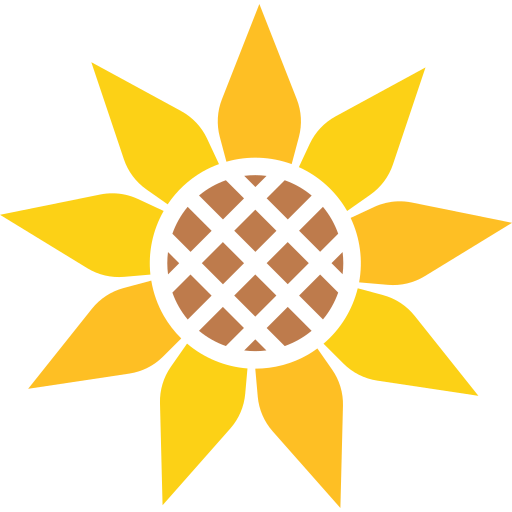自分や家族が心臓病か大量出血を伴う大けがのときは、医師免許を持っていなくても手術をしてよい――もしもこんな制度があったら、あなたは自ら執刀しますか? まさか、ですよね。そんなことをしたら大切な人を死なせかねない。
しかし実は、これと似たようなことが刑事司法の場で起きています。
私が知る制度という制度の中で、刑事裁判の被害者参加制度ほど犯罪被害者にとって酷なものはありません。本稿では、基本的な説明をしたうえで、その理由を解説していきます。例やたとえも使いながら刑事司法の基礎をできる限りわかりやすく書くので、もしあなたや周りの人が同制度を利用するか迷っているなら、事前に必ず読んでほしいと思います。
目次
被害者参加制度とは?
被害者参加制度は、刑事訴訟法(以下、刑訴)で定められた一定の条件のもと、被害者本人、もしくはその法定代理人(典型的には未成年者の保護者)、または委託を受けた弁護士に、刑事裁判手続きへの参加を認める制度です。
参加が認められるのは、被害者側があらかじめ検察官に申し出、かつ裁判所が諸事情を考慮して相当と認めた場合です。
また対象となる事件も限られていて、刑訴316条の33の1号から5号に定められています。具体的には、故意により人を死傷させた事件、性犯罪、業務上過失致死、過失運転致死傷など、人身に被害が及ぶ重大な犯罪が対象とされています。
裁判に参加する「被害者参加人」は、事件に関する検察官の活動について意見を述べ、また説明を求めることができます(刑訴316条の35)。また裁判所が相当と認めたときは、証人の尋問(刑訴316条の36)、被告人への質問(同316条の37)、法律の適用について意見を陳述(=求刑)(同316条の38)をすることが認められます。
本来、刑事裁判は検察官・被告人およびその弁護人・裁判官の三者によって行われます。犯罪に遭った人は事件の証人として証言をするのですが、この制度で参加が認められた場合は、検察の横で裁判に出席し、直接参加することとなります。
被害者参加制度の法的問題点解説
以上のような被害者参加制度には、スタートする前から法的問題点を指摘し、危惧する声がありました。あなたが気付いているにせよいないにせよ、これはちょっとまずい制度なのです。では一体、どこにどう問題があるのでしょうか?
犯罪被害者が遠ざけられていたのには理由がある
「その昔、犯罪被害者は裁判から排除されていました。しかしようやく彼らの真摯な声が世に届き、とうとう被害者参加制度が実現しました。こうして犯罪で傷つけられた人は、被告人に直接質問したり、自分の苦しみを訴えたり、求刑したりできるようになったのです」
――私はテレビでこんな「ハッピーエンドのストーリー」仕立ての報道に出くわしたことがあります。もしかしたらあなたも同じような話を耳にして、そうなんだと納得したかもしれません。しかし、これを鵜呑みにしたら大変なことになります。
残念ながら、間違った情報が平然と世に出回るのはめずらしいことではありません。もともと日本の刑事裁判に関するニュースは法的な説明をせず、レベルが低いと言われてきました。(ちなみに私には、耳にデタラメが流れてきたので嫌気がさし、テレビを消したことが何度もあります。)
犯罪被害者が刑事裁判のゆくえに直接関わることがなかったのは、きちんとした理由があってのことです。それは欠陥や問題点ではないのです。これについては勘違いや流説が多いので、誤解を解くことに重きを置いて以下で解説していきたいと思います。
刑事司法は「国家が被害者に代わって復讐する仕組み」ではない!
まずは、世の中で一番多い誤解を解いていきましょう。その誤解とは、刑事裁判とは「国家が『犯人』に復讐する仕組み」だ、というもの。……「エッ、違うの?」と驚いた読者もいるかもしれませんが、これが一番大事なポイントです。
「犯人」への復讐が目的でないなら、そもそも刑事司法とは何なのでしょうか。以下でその根本的なところを見ていきましょう。
そもそも刑罰って何だろう?―刑事法の根本
刑罰は、本質的には害悪です。人間を捕まえて監禁するなんて、悪いことに決まっているのです。それこそ「犯罪」じゃないですか。
では、国家がそういったことをするのはなぜ正当化されるのでしょうか?
細かい議論はいろいろあるのですが、その根拠は「当該行為には刑罰があると国家が予告することで、犯罪を抑止するため(「一般予防」と呼ばれる)」および「犯罪者自身が将来再び罪を犯すことを防止するため(「特別予防」)」と解されています。
刑罰を加えることは、国家権力の一部です。である以上、こうした刑罰論の大元にある問題は「国家とは何か」です。これを論じたのが、歴史の教科書にも載っているホッブズ、ロック、ルソーらの社会契約論。自然状態において人は自由で平等だが、どうしても紛争が起こる。それを解決する機関が必要になり、人々が社会契約を結んで形成したのが国家である。――ならば、国家による刑罰は公益のためでなければならず、本来は害悪なのだから必要最小限でなければなりません。
したがって、刑事裁判はあくまで国家が国家として機能していくための作用です。犯罪被害者個人のためのサービスではありません。犯罪に遭った人に代わって国家が復讐をしてくれるとか、「犯人」に罰を与えるよう裁判官に頼もうとか、そういうとらえ方は実際とは異なるのです。(ちなみに、金銭的・精神的損害の賠償を相手に直接求めるのは民事裁判。)
なんで誤解しやすいのか?
それをサービスかのようにとらえてしまう誤解は、刑事裁判と聞くとつい「殺人」や「強盗」など、人身に被害がおよぶ暴力的な事件を思い浮かべがちなことから生まれていると思います。
実際の刑事司法は、そのイメージとはずいぶん違います。刑法全体に目を通してみれば、人に暴力を振るって傷つけた、というのとは趣向の違う犯罪がその多くを占めているのに気付くでしょう。たとえば「虚偽公文書作成」「業務上横領」「麻薬所持」「通貨偽造」など……。けっこう地味な感じがしないでしょうか。言い換えれば、国家が刑罰の対象とする行為の種類はさまざまで、その多くには「被害者」が存在しないのです。
それを考えれば、刑事裁判を被害者向けサービスかのようにとらえるのは的を射ないということが分かるでしょう。
国づくりシミュレーションでたとえると
以上のように、刑罰というものを考える際には、「国家とは何か」が起点になります。
これはシミュレーションゲーム風にたとえるとイメージしやすいのではないでしょうか。あなたは空っぽな土地の王様で、これから新しい国をつくっていきます。国=共同体では毎日さまざまなことが起こります。あなたは農業、エネルギー、商取引などあらゆることに対処しつつ、時に紛争が起こるのは共同体の宿命ですので、ルールを作っておかなければなりません。そのうちの一つが刑事司法です。よい制度を整備すれば自由で暮らしやすい国に発展し、人々は幸せになりますが、失敗すれば国は荒れ果て、やがては破綻するでしょう。
刑事司法の大原則との自己矛盾
以上は、よくある誤解を解こう、という話でした。が、同制度の理論と設計にはもっと致命的な問題があります。それは、刑事司法のすべてに通じる大原則「無罪の推定」との間で自己矛盾が生じているということ。制度自体に無理があるのです。
「無罪の推定」とは?
「無罪の推定」とは、「すべて犯罪の訴追を受けた者は、法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定される」という刑事裁判の大原則です。
日本では憲法31条に根拠があり、世界的にも、世界人権宣言11条1項・国際人権規約(人権B規約)14条2項に明文があります。世界人権宣言は「恐怖及び欠乏のない世界の到来」を一般の人々の最高の願望として宣言しており、無罪の推定はそれを実現する方法の一つとして挙げられています。つまり裏を返せば、もし無罪の推定原則がなければ、「恐怖及び欠乏」がある世界になってしまうということ。古くは1789年のフランス人権宣言の時点で、国民主権や自由、平等と並んで「すべての人は有罪と宣言されるまでは無罪と推定される」(第9条)という項目が盛り込まれています。
人類が「無罪の推定」を求めた理由
このように、被告人の無罪の推定は、私たちが我慢して受け入れさせられるものどころか、人類が率先して求めたものなのです。
なぜ人類は無罪の推定原則を考え出し、宣言するに至ったのか。それは、えん罪(濡れ衣)の悲劇防止ためだといえます。
被告人が出てきたら裁判官がみな「有罪だろう」と思ってかかっている法廷を想像してみてください。なら事実上、逮捕・起訴された時点で有罪決定じゃないですか。裁判所には存在意義がなくなってしまいます。
上で説明した通り、刑罰とは本来害悪です。身体の自由や財産、場合によっては生命まで奪うので、刑事裁判の判決は重大です。
しかし人類の歴史には、無実の人が疑いをかけられた時点で事実上有罪となり、たびたび拷問で虚偽の自白をさせられた末、命までも不当に奪われるという悲劇がありました。それは一件二件たらずの例外ではなく、数えきれないほど大量に……。あの人もこの人も、あなたも私もみな、誰かから疑いをかけられたらもう終わり。それでは生きた心地がしませんよね。そのような「恐怖」が起こるのを防止するため、「検察官が犯罪の事実を証明できない限りは被告人は無罪」という大原則が作られているのです。
ところが被害者参加制度はどうか。裁判に参加した人は、被告人が当然「犯人」だという前提ですよね。つまり、被告人は有罪だと推定しているわけです。
後でもう一度改めて述べますが、人類が多大な犠牲の上に築き上げた刑事裁判の根幹を否定してしまうことは、被害者参加制度最大の問題点といえるでしょう。
刑事法について何も知らないワイドショー出演者や歳若い文学青年が、感覚と思い付きで「刑事裁判は加害者の人権ばっかり守っているけれど……」などと口ずさんでいることがあります。それがどれほど的外れか、バックグラウンドを知ればよく分かったのではないでしょうか。
もしも被害者参加制度が画期的ですばらしいものだったら、世界の刑法学に一大ムーブメントを引き起こし、各国がこぞって検討・導入するはずです。しかし、一国たりともまねしようとはしません。その背景には、人類の闇の歴史と、それを克服せんとする切なる願い、そして筋の通った理由があるのです。
厳罰化の流れのうちに生まれた、ないはずの制度
では、なぜこんなに問題点だらけであるにもかかわらず、被害者参加制度は実現したのでしょうか?
同制度は、犯罪被害者が厳罰化を求める流れのうちに成立したといわれています。かんたんに言えば、「あいつをもっと罰してほしい」という感情です。純粋に理論だけで考えれば、参加人が検察官の横で「死刑は絶対やめてください、懲役5年を求刑します」などと刑を軽くするよう求めることもあり得るはずなのですが、それが意識すらされないのは、同制度が厳罰化の流れの一端であることをよく表しているといえるでしょう。
犯罪被害者が求刑をするようになるというので、制度が始まったころ関係者が騒然としていたことを私はよく覚えています。裁判員制度とセットで始まることも相まって、感情論やポピュリズムを排さなければならない刑事司法が復讐劇場と化しかねないと、危惧が叫ばれてきました。被害者参加制度は、刑事司法と本質的に矛盾する、本来はありえない、あってはならないものなのです。
支援は別の適切な方法で
もっとも、犯罪被害者の声の全部が全部誤りだったとは言いません。この社会ではどうも犯罪というものが現実的に考えられておらず、生活や心への配慮、その後の支援にはとぼしいところがあったからです。
しかし、だからといって話を被害者参加制度につなげるのは飛躍であり、無理があると言わざるを得ません。目的に対して手段が合致していないからです。
本当に充実させるべきなのは、支援や社会の在り方などです。国家権力たる刑事司法の仕組みではありません。
補助金による経済的支援は、ここ数十年で拡充が進んできています。すでに犯罪で深い傷を負った人が二次被害を受けないための配慮、またプライバシーへの配慮は、対応する警察官の教育や、証人として出廷する際の精神的負担軽減策によって実現できますし、実際これらも進んできました。金銭的・精神的損害の賠償請求には、民事訴訟があります。
このように、理不尽にも犯罪に遭われた方々を支えるのは、支援という目的にぴったり合った、正当な手段によるべきです。
制度が被害者にとって酷な7つの理由
以上が法的問題点となりますが、いかがだったでしょうか?
刑法を考えるとは国家とは何かを考えることにつながるので、どうしても理論的で抽象的になります。もしかしたら、あまり実感がわかないという人もいるかもしれません。なので、ここからは個々の事件のもっと具体的なところを見ていきましょう。
私が強調して言いたいのは、被害者参加制度は被害者にとって酷だということです。被告人にとって、ではありません。以下はその角度から、どこがどう酷なのかを7つ指摘していきたいと思います。
全体を通して見て、被害者参加制度の性質の悪さは、犯罪に遭った人に実際には起こり得ないことへの期待を抱かせてしまうところにあると私は考えています。
「真犯人」が反省してくれるとは限らない
犯罪に遭った人が何より求めているのは、加害者の心からの謝罪でしょう。犯罪によって理不尽に奪われたものは、金品や心身の健康だけではありません。傷つけられたのは、人格の尊厳です。加害者は非を認めて、自分が犯罪行為によって否定した人格の尊厳を肯定し直すべき。もし反省しないなら、それは重ねて侮辱と危害を加えるに等しい。だからやったことへの反省と心からの謝罪を求めたい――。
ただ、刑事裁判に参加して被告人に質問・求刑することは、果たしてこの願いを実現する手段となるのでしょうか。
検察官の横に立ち、「犯人」(※被告人が真犯人とは限らないが、ここではそうだと仮定する。論に無理が出るのは、制度に矛盾があるせいである。)に質問したとします。「なぜこんなことをしたんですか」「私がどれほど苦しんでいるか分かりますか」「真実を語ってください」など、言いたいことはいくらもあるでしょう。
しかし、被害者が法廷でどれほど問い詰めようが、厳罰が下ろうが、反省して真摯に謝罪するかどうかは「犯人」次第です。
たとえば恋愛で、片思いの相手に自分を好きになってほしいと願ったとします。けれど、その人がふり向いてくれるどうかは相手次第じゃないですか。真剣な想いを重ねても、がんばっておしゃれしても、プレゼントを渡しても、相手が好きじゃないというなら、もうどうしようもない。
これと同じ原理です。
質問された「犯人」は、自分はやっていないと言い張るかもしれません(くり返しますが被告人は無実かもしれない。えん罪については下で改めて扱います)。無言を通すかもしれません。あるいは反省するどころか、侮辱、罵倒を投げつけるかもしれません。たとえば「犯人」が「悪いのはお前のほうだ」と主張するのは、二次被害(カタカナ言葉ではセカンドレイプ)の典型です。一応配慮の措置がなくはないといえ(刑訴316条の39)、裁判に参加して被告人と直接やりとりしたがために、被害者がさらに傷つく可能性があります。
こうしたことが起こるのは刑事司法の欠陥のせいではありません。無論、犯罪に遭われた方の落ち度でもありません。すべて「犯人」の性格のせいです。また、にわかに信じられないかもしれませんが、世の中には「反社会性パーソナリティ障害」といって、他人に危害を加えても罪の意識や後悔を感じない人間も存在しています。
参考リンク:人格障害の特徴と犯罪の関係は?
「犯人」に心の底から悪かったと思ってほしい気持ち、誠意ある謝罪を求める気持ちは自然かつ正当です。「犯人」がこの世で生きていること自体が苦痛だという気持ちもわかります。しかし、被害者参加制度はその気持ちに応えられるわけではありません。なぜなら、制度うんぬんではなく、そもそも物理科学的に、反省しない「犯人」を反省させる方法はこの世に一つもない。愛の妙薬が魔法でしかないのと同じです。
たとえ刑事裁判に参加しても、煮え切らない思いは残るでしょう。犯罪の被害に、さらなる苦しみが加わるかもしれません。そして期待外れな結果になったとしても、それはいかなる制度のせいでもないので、独りで受け止めるしかありません。……酷ではありませんか。
(※大事なことなので一歩踏み込んでおきますが、加害者が謝罪しないからといって、その行為が悪くなかったことにはなりません。悪いことは悪いです。また、加害者からの謝罪を得られなくても、被害者の人格の尊厳は100パーセント完全なままで減ることはありませんので安心してください。私がなぜこういう話をしているかに興味があれば、こちらをどうぞ。)
(※くどいようですが、本稿のこの部分では語弊があること承知で被告人の有罪を前提としたような表現を使っています。刑事裁判の鉄則は無罪の推定なので、くれぐれも誤解のないようお願いします。)
被害者の意見は、決して通らない
同制度は、犯罪被害者が検察官の横で求刑できるというものでした。「この人を懲役10年にしてください」などと法廷で言えるというのです。こうなれば当然、参加人は判決が求刑通りになるよう期待するでしょう。
しかし現実には、判決は、被害者参加人の意見通りになることはありません。
なぜなら、それではもはや裁判ではなくなってしまうからです。上で説明した通り、刑事裁判は国家のシステム。特定個人へのサービスではないのです。
また、裁判は公平・公正であることが命です。被害者がどういう性格で、どんな信条を持った人か。事件のことをどうとらえたか。家族はどんな人物か、あるいは家族がいたかいないか――一口に犯罪被害者といっても、人柄や考え方、家族関係は千差万別です。たとえば、同じ過失運転致死の裁判なのに、遺族がたまたま激しい性格で厳罰を求めたから罪が重くなったとか、逆に血の気の少ない人だった、あるいは車にはねられたのが遺族のいない天涯孤独な人だったら罪が軽くなった、としたらどうでしょう。もしそういう個別の事情で判決が左右される裁判所があったら、もう信用できないですよね。

制度を利用した参加人の中には、求刑通りの判決が出たので「自分の思いが裁判官に伝わったから、参加してよかった」と感じた人もいるそうです。しかし実際には、それは偶然の一致にすぎません。すでに述べた通り、刑事裁判は特定個人ではなく、すべての人のために行われます。また、裁判官は独立して考えて判決を出します。「思いが伝わったから」その判決になったわけではないのです。
判決だけではありません。裁判への参加を希望する段階でも、その後の証人尋問、被告人への質問、求刑に際しても、裁判所がそれを認めるまでには刑事訴訟法に事細かな規定が設けられています。事件によっては参加が認められるとは限りませんし、法廷に出席したとしても思い通りに何でも言えるわけではないのです。
被害者参加制度などと聞いたら、まるで被害者の希望が判決に反映されるような期待を抱いてしまうかもしれません。しかしこれは公平・公正が命の裁判。決して思い通りにはなりませんし、ならないから正当なのです。
のちに思いが変わっても、その時にはどうにもできない
犯罪に遭うのは、理不尽な大惨事です。日常から真っ逆さま。混乱と怒りの嵐。終わりのない苦しみと悲しみ。犯罪の直後、「犯人」に「奪ったものを返せ!」と激情をぶつけたくなるのは人間としてきわめて自然です。
ただ、5年、10年、20年と時が経つうちに、被害者の思いが変わっていくのはめずらしいことではありません。
「あの時は裁判に参加してああ言ったけど、今では……」そんな心情の変化が生まれたとき、被害者参加制度には応えようがありません。裁判に参加して言ったことは確定事項であり、それを後から変更することはできないのです。
なぜなら、これはあくまで国家権力の作用たる刑事裁判だからです。裁判所は、心のケアを行う病院とは別なのです。
のちに制度が変わったら
先に解説した通り、被害者参加制度は法的に根本的な問題を抱えています。将来的には立法によって撤廃、あるいは原型をとどめないような抜本的改革が行われるでしょう。
では、それがなくなった時、被害者参加人が求刑まで行った判決はどのような評価を受けるのでしょうか。
自己や大切な家族のためよかれと思って参加したのに、何十年後、裁判の公正さに疑問符がついてしまった――そんなことが将来現実に起こり得ます。すでに参加した方にとっては残酷な現実かもしれません。しかし、法的に問題だらけで施行される前から批判が多く、本来なくて然りの制度を利用するとはそういうこと。だから酷だと私は言っているのです。
犯罪被害者がえん罪を起こすという悲劇のシナリオ
テレビのニュースから受ける印象とは違うかもしれませんが、刑事裁判の被告人は事件の真犯人とは限りません。被告人は、濡れ衣を着せられた無実の人かもしれないのです。たとえ被害者が「あの人がやった」とどんなに固く信じていても……。
足利事件を思い出してほしい
さて、足利事件とは、栃木県足利市で起きた幼女殺害事件で有罪とされ無期懲役が確定した菅谷さんという男性が本当は無実だったというえん罪事件です。有名な事件なので、どこかで耳にはさんだことがあるのではないでしょうか。
濡れ衣のために、菅谷さんは人生の大半を獄中で過ごすことになりました。彼が失った人生は、もう取り返しがつきません。また見逃せないのは、何十年も菅谷さんが「身代わり」にされていたため、幼女殺害事件の「真犯人」は今なお逃げ続けているという点です。
もしも今日あなたがご遺族の立場だったら、裁判に参加して「犯人」(正確には被告人、つまり菅谷さん)に「自分がしたことを反省していますか」と質問したり「厳罰に処すよう求めます/死刑を求刑します」と意見を述べたりしますか? ……想像しただけでも身の毛がよだちますよね。
無実の人の人生を破壊してしまう危険性
被害者参加人は、主観では、「極悪人」に反省と心からの謝罪を求めて検察官の横に立ったはずです。
ところがもし冤罪だった場合、参加人がやっていたことは一体何だったのか。
――無実の人を「犯人」だと決めつけ、反省しろと怒鳴りつけた。厳罰を求刑して、刑務所へ送り、それを喜んだ。また、無実の人を夢中で糾弾している間、「真犯人」はずっと警察に追われる心配なく逃げおおせていた。――
厳しいですが、これが現実です。直視しなければなりません。
望んだことからしたら突拍子もないことをしていた、と気づいた時、えん罪被害者の人生はすでに破壊されています。謝ったところで取り返しはつきません。検察の席で刑事裁判に参加する以上は、この失敗をしてしまう危険性から免れることはできません。
無実の人を死刑に処してしまう危険性
何度も言いますが、被告人が真犯人とは限りません。現在の日本は、よりによって死刑がある国です。被害者参加人が死刑にしてくれと叫び、結果として死刑に処されたその人が、本当は無実だった――そんな衝撃的なことも、決して絵空事ではないのです。
先に述べた通り、判決を決めるのはあくまで裁判官です。参加人の意見は反映されません。しかし「その人を死刑にしてください」とまで言っておいて、「私は死刑判決に関係ありません」と開き直れるでしょうか。
犯罪の被害者だったはずの人が、えん罪の加害者になってしまうのです。罪なき人を殺害してしまうという、絶望的な結果。この場合、濡れ衣を着せられた人はもうあの世ですので、謝ることすらできません。どんな言葉でも言いようのない葛藤と苦悩は、永遠に続くでしょう。
犯罪被害者が重大な覚悟を決めなければならないという、酷なシチュエーション
刑事司法にかかわるのは厳しい職業です。もし自分が判断を誤ったら、無実の人を破壊してしまうからです。警察官や検察官、裁判官は、その重責を承知の上でその職に就いています。
それが、今しがた重大な犯罪に遭ったばかりの人はどうでしょうか。
ただでさえ傷つき苦しんでいる犯罪被害者や遺族・親族が、この重責を背負うのですか。覚悟は決めたのか。いえ、覚悟どころか、その重責が頭にないうちに参加してしまったというのが実際のところではないでしょうか。
覚悟があろうがなかろうが、知っていようがいまいが、刑事裁判に参加する以上は事実としてこの重責を負うことになります。シチュエーションとして酷ですし、そんな状況を生んでしまった制度に私は強い憤りを覚えます。
被害者だったはずの人が、人類を攻撃する側に……
凶悪犯罪に遭ったり、家族を殺された人がえん罪を引き起こすなんて、想像しただけで気分が落ち込んだ……という人もいるかもしれません。
しかし被害者参加制度には、それ以上の、逃れることのできない過酷さがあります。先に解説した、裁判に参加するということ自体が、自覚の有無にかかわらず刑事司法の大原則「無罪の推定」を否定してしまうという法的問題です。
上記ではこの制度がいかに酷であるかを述べてきましたが、中には問題ない(ように見える)事案もあるかもしれません。たとえば、
- 参加人が検察の席から問い詰めた結果、「犯人」がついに反省の言葉を口にしてくれた(もっとも、これが被害者参加制度のおかげだとか、だから存続させたほうがいいというのは早計だが)。
- 判決が参加人の求刑通りになった。裁判所に思いが伝わったのだ(先ほど述べた通り、これは主観でしかなく事実とは異なる)。
- 被告人が「真犯人」だったのでえん罪ではない(もっとも人間のやることなので、絶対的な真実は誰にも確かめようがないが)。
結果良ければすべてよしじゃないか……とはいかないのが、被害者参加制度最大の過酷さだと思います。この制度は、使った人に無罪の推定原則を自動的に破らせてしまうのです。
犯罪被害者は、人生を普通に歩んでいる途中で突然、犯罪に遭うという巨大な理不尽に引きずり込まれた、何の罪もない人でした。
その被害者だったはずの人が、被害者参加制度なんかがあるために、自覚のあるなしにかかわらず、人類が多くの犠牲の上に築き上げてきた刑事司法を破壊し、世界に「恐怖及び欠乏」を呼び戻す者へと変貌していってしまう。こんな悲劇が地球上にあっていいものでしょうか。
ただでさえ大変なのに、背負う負担とプレッシャーが重すぎる
殺人や殺人未遂、性犯罪などの被害に遭ったら、ただの精神状態ではいられません。その日から人生は変わってしまいます。
その大変な状況にある人に、被害者参加制度は、裁判に参加するか否かの選択を迫ります。
刑事司法がどういうものなのかを知らなければ、参加・不参加の判断を理性的に下すことはできません。ただでさえつらい状況にある犯罪被害者が、裁判が始まるまでのごく限られた時間で、勉強までしなければならないのです。基礎知識であれば本稿でカバーできるように書いてきましたが、六法のなかでも刑法理論はむずかしいので有名です。法学部の一年生が一年間苦しむ科目を、よりによって精神状態のひっくり返った人が……。傷ついた人に、むちを打たないでほしい。自分を大事にすべき時のはずです。(もっとも、参加人の大部分はそれさえ意識しないまま進んでしまったというのが実情であり、後で本当のことを知った時にどれほど後悔するだろうと思うと胸が張り裂けそうなのですが。)
また、同制度が刑事司法の大原則を曲げたものである以上、法廷でした発言に対して批判意見があがる可能性はあります。批判する側が良識ある人だった場合は、被害者の心を斟酌し、配慮ある言葉を選ぶでしょう。しかし、内容的には筋が通っていて厳しいものとなります。こうなったらどこにも逃げ場はありません。悪意ある人が吐き捨てる誹謗中傷は荒々しくとも空っぽなので、ある意味では精神的にまだましかもしれません。
犯罪に遭ったばかりで大嵐まっただなかの人がこれらを考慮し、選択し、発言するのは負荷が重すぎる。あまりに酷で、目も当てられません。
まとめ:主観と客観の埋まらない溝
以上、被害者参加制度が犯罪被害者にとって酷な理由を7つみてきましたが、いかがだったでしょうか。
根本的に無理矛盾のある制度は、どこまでも苦々しいです。こうして順々に見てきて目についたのは、犯罪被害者の方々が主観で頭に想像していることと、その言動が実社会で持つ客観的な意味に、埋まりようのない大きな隔たりがあるということでした。
被害者参加制度は童話か何かに出てくる幻惑の森みたいなものだ、とイメージしてみてはどうでしょうか。ある日突然苦しみに落とされた人の目に、その森はなんだかすばらしいところのように映る。奥には求めるものがあるに違いないと信じて足を踏み入れる。だけど、進んでも進んでも、求めるものはどこにもない。そして暗くあやしい森をさまよううちに、やがてはその姿と心が変貌していってしまう……。実は最初から、周りの人々には、それが危険な森で、どんなに奥まで進んでも求めるようなものはないと分かりきっているのですが。
同制度の本当のところは、すでに裁判に参加した人にとっては「知らぬが仏」かもしれません。しかし事実は事実です。
もとは被害者だった人が、それをきっかけに悪い方向へ行ってしまう。これほどやるせないことはありません。
おわりに
自分や家族が心臓病または大量出血を伴う大けがのときは、医師免許がなくても手術をしてよい――もしもそんな医療システムがあって、もしもそれを利用する人がいたら、世の中はどんなことになるでしょうか。一応練習してから自分の傷の縫合にのぞんだけれど、膿んでしまったあげく、自分の体に素人仕事の縫い痕が残ってしまった。無免許の家族が手術室でメスを手にするようになったら、医療に対する社会からの信頼が落ちてしまった。大切な我が子を、自分の手で死なせてしまった。そんなつもりじゃなかったのに――。
自分や大切な人を本当に救いたいなら、何もかもに自分が出て行って手をつければいいというものではありません。やる気と思いだけでは、良い結果にはつながらない。周りをよく見て、適切な方法をとらなければ。このことは、刑事裁判でも同じです。
もしあなたが犯罪被害者や関係者で被害者参加制度を利用するかどうか迷っているなら、悪いことは言わないので制度は使わず、従来どおり証人として出廷することをすすめます。これ以上傷つかないでほしい。自分を大事にしてほしい。過去には大変な目に遭ったとしても、どうかその後は自由に生きてほしい。それが私の切なる願いです。
最後になりますが、犯罪に遭われた方・ご遺族の方には心よりお悔やみ申し上げ、結びとさせていただきます。
関連記事・リンク
著者・日夏梢プロフィール||X(旧Twitter)|Mastodon|YouTube|OFUSE
映画『レ・ミゼラブル』レビュー – 舞台は19世紀フランス。パンを一切れ盗んで19年も強制労働をさせられていたジャン・ヴァルジャンを主人公とする有名な小説のミュージカル映画版です。被害者参加制度と直接の関係はないんですけど、人権保障がない世界での刑罰がどれほどひどいものかが映像でわかりますので、よければどうぞ。
人格障害の特徴と犯罪の関係は? – 「あの人はこんなひどいことをしておいて、どうして少しも反省しないのか」――その答えとなる事物をいくつも解説しました。この世には、反省もなにも、そもそも良心の呵責を感じない人間が存在している、ということはご存知でしょうか。
ポピュリズム事例集―日本の小泉政権からトランプ大統領まで – 近代司法の大原則を曲げる突拍子もない制度は、いかにして実現してしまったのか。その政治的背景たる小泉政権について解説してあります。
法令検索・刑事訴訟法 – 刑事訴訟法の原文です。一般向けの説明は法務省ホームページなどにもあります。一から勉強するなら刑法のテキストがありますけど、まわりに犯罪の被害に遭われた方がいらっしゃるなら、どうか無理をさせず、大事にいたわってあげるようお願いします。