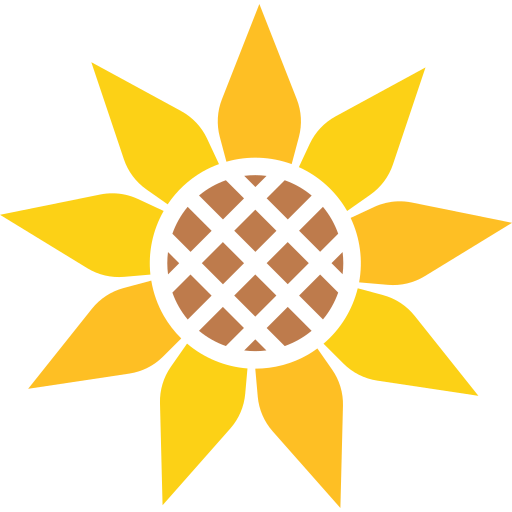皇室メンバーがどんな人と結婚するのか。家族関係はうまくいっているのか、亀裂があるのか。病気になっているのか、病状はどうなのか。――こうした皇室の話題はメディアに絶えずのぼっており、ネット上では並外れた数のコメントが付くほど人々から注目が集まっています。
しかし、こんなにたびたび取り上げているにもかかわらず、メディアは皇室・天皇について「核心的な」議論はしようとしません。話題を大衆の目に楽しい範囲にとどめ、頑として踏み込まない。そういう自らの態度すら他人事のようにながめている。テレビ、新聞、出版、映画などにおいて、皇室・天皇へのタブー視が顕著となっているのもまた事実です。
なぜひとたび皇室関連となると、メディアはまっとうな言論や議論を避けて通ろうとするのでしょうか? 実は、その背後には「闇の勢力」が深く関わり、天皇・皇室タブー視の風潮を何十年も陰から牛耳ってきました。今回は、そんなメディアの裏事情に迫ります。
目次
メディアが恐れる「脅迫」の影
テレビや新聞、雑誌等が暗黙のうちに皇室制度の議論をタブー視する背景事情は、実はとてもはっきりしています。右翼団体です。
黒塗りのワゴン車にスピーカーを取り付け、日章旗を掲げる街宣車(画像リンク)。こういった「街宣右翼」と呼ばれる団体は、企業や行政機関などを取り囲んで大音量でがなり立て、自らの要求をのむよう脅迫します。
メディアがこぞって皇室の話題を当たり障りない範囲にとどめておきたがるのは、そうした右翼団体による脅迫や、その背後にちらつく闇組織とのつながりを恐れてのことだといわれています。
右翼団体による抗議は、なにも皇室や天皇制を直接的に批判した場合だけに行われるのではありません。実際にはそうでなくても団体側が「批判している」と受け取れば、あるいは団体側が「表現に問題あり」と判断したなら、社にはあとに述べるような暴力的な抗議が押し寄せます。
メディアにしてみれば、脅迫は、来るのか来ないのか、その言論を世に出してみるまでわからないわけです。「もしかしたら脅迫されるかもしれない……」という不確定な不安から、テレビ番組や新聞、出版などは萎縮し、それが皇室のタブー視へつながっているのです。
メディアを脅迫する闇組織とは?
では、メディアを脅迫する右翼団体とは、具体的にどのような団体なのでしょうか。
警察庁が毎年出す暴力団情勢の統計には「政治運動等標ぼうゴロ」というのが出てくるのですが、これはだいたい街宣右翼のことを指しています。警察庁の「平成30年における組織犯罪の情勢【確定値版】」によれば、「政治運動等標ぼうゴロ」は全国で5100名(暴力団構成員全体は30500名)とされています。
広域暴力団はたいてい傘下に右翼団体を抱えています(『暴力団』溝口敦、192頁)。そうして企業や行政機関に対し「要求をのまなければ右翼団体が黒い街宣車で社屋を取り囲み、大音量でがなり立てる」と脅迫するのです。別の見方をすると、そういった右翼団体のバックには暴力団がついている、ということになりますね。
「暴力団」とは、法律の定義によれば、「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう」(暴対法2条2項)とされています。
条文カッコ内の「構成団体の構成員」についてですが、闇組織の多くはピラミッドが積み重なった形態になっています。トップの団体(一次団体)は下にいくつもの団体(二次団体)を抱えていて、二次団体の傘下にもまた別の団体が……というように、団体の下に団体が付いているピラミッド構造です。もっとも大きな組織では、五次団体まで確認されているといわれています。つまり、暴対法の定義には、頂点の団体のメンバーだけではなく、末端組織の構成員に至るまですべて含まれるということになります。
警察庁が毎年刊行する『白書』をみると、警察は犯罪組織の「伝統的資金獲得犯罪」として、薬物や賭博と並んで「恐喝」を挙げていることがわかります(平成30年『白書』134頁)。
「恐喝」とは、人を「脅迫」して金品をゆすり取ることをいいます。たとえば、見るからに恐ろしい風体の人物が一般商店に顔を出し、犯罪組織の名をちらつかせながら「用心棒」をするのなんのといわれのない理由をつけて金を要求したので、「払わなかったら恐ろしい目にあうのでは……」とふるえあがった店主がお金を渡してしまった、というのが典型です。こういった恐喝が、犯罪組織の主な資金源の一つになっています。つまり、犯罪組織のメンバーとは、「暴力」で人を脅して自分の要求を押し通すプロなのです。
日本の「闇の勢力」の趨勢
明らかに不当な要求です。ならばそんな要求はのまなければいいし、あるいはあまりの怖さに払ってしまったならあとで警察を呼べばいい、と思いますよね。
ところが、信じがたい話ですが、日本の大規模な株式会社は1970年代までほぼ例外なく、こうした「闇の勢力」に、毎年、金銭を贈っていました。株主となった組員(「総会屋」と呼ばれている)が「要求額を払わなければ、株主総会で議事進行を妨害する」と会社を脅し、会社側は穏便さの対価として彼らにお金を支払っていたのです。「総会屋」は日本企業限定の翻訳不能な存在なので、外国語でもそのまま”sokaiya“と記されます。
この独特な悪習に対し、欧米の投資家から「日本の会社はマフィアに支配されている」と批判の声が上がりました。これをきっかけに1981年、「(会社が)株主の権利の行使に関して利益供与すること」を禁止する条項が定められたのは、わが国の商法・会社法のひとつのターニングポイントとなっています。結果、総会屋の活動は衰退した(『日本の会社法』新訂第9版 205頁)といわれ、現在では警察の統計でもほとんど確認されていません。このような「総会屋の禁止」をはじめ、様々な対策が進んだことにより、資金源を失った暴力団が隠れミノとして右翼に流れた、とも報告されています。
闇組織の動向は、これまでも、時代とともに移ろってきました。近年もまた、情勢は日に日に移り変わっているといわれています。警察および独立した民間の双方から「伝統的な犯罪組織が崩れている」との報告がある一方、市川海老蔵殴打事件で注目を集めた「半グレ」と呼ばれる新たな形態のグループが、オレオレ詐欺などでのしてきているとされています。
議論は正当、脅迫は不正―その法的根拠
ただ、そもそもここで問題となっているのは、脅迫者のバックについている闇の勢力が伝統的な犯罪組織かどうか、組織か個人か、などではありません。「暴力」によって自らの思想や要求をごり押ししようとするテロ行為自体が決して許されるものではないからです。
メディアが皇室や天皇について活発に議論するのは、タブーどころか、まったくもって正当な行為です。憲法は国民に表現の自由を保障していますし、そうやって活発な言論を行うことがメディアの使命、そして存在意義でもあるからです。メディアがもしそれに背を向けるなら、言ってしまえば人の役に立っていない、存在しているうちに入らないことを意味します。
他方、生命・身体・自由・名誉または財産に「害を与えるぞ」とおどす「脅迫」、および、いわれのないことを行わせる、または正当な権利行使を妨害する「強要」は、それぞれ刑法222条、223条が定める犯罪です。
なので、本来は、脅しを受けたメディアが皇室についての議論をすごすごと「自主規制」する理由などありません。
では、天皇・皇室について論じるべき報道・出版等各社は、なぜ「脅し」の影に対して、一般常識にかなった対応をしないのでしょうか。「正当な行為」に対する「不当な要求」をのまなければならないほど、闇の勢力は恐ろしいのでしょうか?
過去の主要な脅迫事件とその影響
メディアが抱くという恐怖、そしてそれが皇室タブー視に至る原因を探るには、過去に実際起きた脅迫事件がどのようなものだったか調べる必要があります。
ここでは例として、特に大きな事件をまとめます。
出版社・中央公論社社長宅での殺人・傷害事件(1960年)
まず、1960年には、中央公論社の雑誌に掲載された小説『風流夢譚』を「不敬」だとした少年が、同社社長宅に侵入し、居合わせた家政婦を刃物で刺して殺害、社長の妻に傷害を負わせる事件が発生しました(社長本人は不在)。少年は、犯行前日まで右翼団体に所属していました。事件は同社社長の名をとって「嶋中事件」と呼ばれています。
事件は社会を震撼させましたが、その後も中央公論社への抗議は続き、同社は以後、論調を変更するに至りました。
なお、同1960年には、日比谷公会堂にて演説中だった日本社会党委員長・浅沼稲次郎が、右翼の少年に刺殺される事件がありました。浅沼稲次郎暗殺事件は、戦後民主主義におけるもっとも残忍なテロの一つに数えられています。
映画会社・東映への脅迫事件(1980年)
1980年には、映画会社・東映の映画『徳川一族の崩壊』について、孝明天皇暗殺の描写を「不敬」だとした右翼団体の街宣車が東映に押しかけて抗議活動を行いました。
東映は、この事件を大きなきっかけとして、大作時代劇の制作を打ち切りました。
出版社・河出書房新社への脅迫事件(1983年)
1983年には、河出書房新社が雑誌に掲載した小説『パルチザン伝説』を「不敬」だとして、右翼団体の街宣車が同社に押しかけました。
1980年代には、ほか複数の出版社やタレントのタモリなどに対し、同様の脅迫事件が相次いでいます。
長崎市長銃撃事件(1989年)
1989年、昭和天皇の戦争責任に言及した長崎市長・本島等が右翼団体幹部に銃撃される事件がありました。長崎市長は全治1か月の重傷を負いましたが、一命はとりとめました。よって、銃撃は殺人未遂事件となりました。
本島はその後も長崎市長を続け、再選を目指した1995年に対立候補に敗れて政界を引退しました。
長崎市長銃撃事件は、オウム真理教事件などと並ぶ、戦後最悪のテロの一つとされています。
過去の事件からわかること
闇組織の暴力性
過去の脅迫事件を洗い出せば、その犯行は極めて暴力的、そして残虐なことがわかります。凄惨な殺人事件までありました。
「刺し殺された」「銃撃された(=拳銃所持は違法なので、犯人は犯罪組織の人間だということを意味する)」となれば、メディア各社で働くジャーナリストが「怖い」と感じるのも無理はないでしょう。
脅しに極度に弱い―日本企業の体質
しかし、くり返しますが、メディアが皇室にかんする言論・議論を行うのはいたって正当な行為です。間違ったことをしていないのだから、堂々としていればいい。「脅迫」に対しては、一般社会の常識にかなった「大人の対応」をすればいい。テロを批判すればいい。頭を下げる理由はありません。
いまはなき”sokaiya(総会屋)”は、「氷山の一角」にすぎなかったといえるでしょう。

1980年代以降の会社法改正により、”sokaiya(総会屋)”はつぶされました。しかし、「『脅し』に極端に弱い体質」という日本企業の本質的な問題は、決して解消されていないのです。
脅されれば、相手が闇組織の人間であれ、何でも言いなりになる。いたって普通な企画でさえ、世に出す前にコソコソ引っ込める。とんだ屁理屈や言いがかりに対して、腰低く、言われたとおりにする。これまで、メディアを含む日本企業は、脅迫者が思い描いた通り「威迫」におそれおののき、不当な要求をのんできました。これは言い換えれば、脅迫者の望みをことごとく叶えてきた、ということにほかなりません。
物事の善悪、立場、社会への影響、自らの使命や責任などをすべて無下にする日本企業の「極端な臆病」は、いいかげん解消すべき悪習です。
「菊のカーテン」を作ったメディアの責任
天皇の「地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」(憲法1条)と定められています。
ところが、当の国民は、天皇・皇室について実情をよく知らない、タブー視の風潮が蔓延してまっとうな議論ができない状況にある。これは大問題です。
まず「知らない」というのは、すでに使い古された「菊のカーテン」という言葉が存分に表しています。宮内庁は、民主主義国家の行政機関にそぐわぬ閉鎖性と秘密主義で知られています。公式資料は宮内庁によって編纂されるので、皇室に関してマイナスとなる情報は表に出る前に削除されてしまっている――歴史研究者等からは、そういった嘆きの声が絶えません。いま皇室では何が起こっているのか。国民にしてみれば心配も多々あるのに、すべての真実は「菊のカーテン」の向こうです。
自分の国の「象徴」について、主権者国民に、知る手立てがない。
これでは「総意」もなにも、国民は意思決定ができません。自分が知らないことに対しては、なんの意見も持ちようがないからです。平たく言うなら、「天皇についてどう思う?」と聞かれても、その天皇の実情を知らないなら、自分なりの考えを出しようがありません。話題の頭数は多くても、それらはことごとく週刊誌レベルにとどまっています。
天皇・皇室について「核心的な」議論がなされない状況は、すでに長々と述べてきた通りです。
論点は多々あります。皇室祭祀への支出は憲法の政教分離原則に違反しないか。天皇・皇室の現状は事実上「内閣の奴隷」ではないのか、もしそうなら今後どのような在り方を目指すべきか。女性天皇という論点は、議論の末に何らかの結論が出されたのではなく、ただ放置されて今に至ります。また、元号はどうでしょう。新元号の決定に際して、主権者国民は「何になるかなー」と完全受け身で待つことしかできず、案を出すことも、投票することもできませんでした。新元号の決定に関し、たとえば憲法学者の水島朝穂早大教授は「実は(1979年の)元号法制定をめぐってはさまざまな議論があった」と指摘したうえで「国民主権原理と世襲君主制を絶妙なバランスで合体させた象徴天皇制という装置が存続していくには、主権者国民の生活に大きな影響を及ぼす元号について、これを国民代表からなる国会で法律をもって定めるべしとする有倉教授の指摘には合理性があるように思われる」(「元号は政権の私物なのか――元号法制定40周年」)との見方を示しています。
このように、議論すべきことが山と積み重なっているにもかかわらず、メディアは1960年のテロ以来、60年もの長きにわたり、脅迫者の顔色ばかりをうかがって「自主規制」に精を出すという、見当はずれな努力を続けてきました。

メディアには、街宣車ではなく、国民のほうへ目を向けてほしい。報道はその社会的使命を高く掲げ、これまで「自主規制」がおよぼしてきた日本社会への悪影響を直視してほしい。これからしようとしている「自主規制」が私たちの未来に与える損害を、論理立てて想像してほしい。私はそう言いたいのです。
暴力を「怖い」と感じるのは、生身の人間としては自然な反応でしょう。しかし視野をもう少し横に広げ、考慮に入れる時間軸をもう一歩のばせば、「脅迫」の見え方はがらりと変わります。闇の中でしかうごめくことができない犯罪組織と、一般人がまっとうなことすら口にできない世の中、どちらが「怖い」のか。一件のテロと、テロがまかり通る恐怖下での日々の暮らし、どちらが「怖い」のか。
毅然とした態度でのぞまないほうが、よっぽど「怖い」ではありませんか。
天皇・皇室について議論できない風潮は「菊のタブー」といわれますが、1960年以降このタブーが形成された過程には、メディア自身の「極端な臆病」にも一定の責任があると言わざるを得ません。
本来、報道機関は、いかなる権力からの圧力にも屈することなく、真実を伝えることで市民の自由を守る社会的使命と責任を負っています。にもかかわらず、日本の報道各社は、「極端な臆病」という世にも奇妙な形で、言論を行う身でありながら、自分みずから「タブー」を形成するのを助けてきた。出版や映画なども、「自主規制」の歩を同時進行させてきた。さすがに「身から出たサビ」は言い過ぎかもしれませんが、「脅迫」されたら最後まわりが一切見えなくなり、不当な要求をのみ、脅迫者にタブーの風潮を貢ぎ、自らのあるべき姿を放棄することで、結局のところ墓穴を掘ってきたのは事実です。
その「極端な臆病」の巻き添えになったのは誰でしょう。視聴者、読者、そして国民ではありませんか。
新元号の決定や退位・即位の礼に際し、メディアはこぞって事実や論点の報道を放棄するという大失態を演じました。これからはしっかり勇気を持ち、一般社会の常識にかなう毅然とした対応で、ジャーナリズムのあるべき姿を守ってほしい。今回は、メディア各社への叱咤激励で結びたいと思います。
関連記事・リンク
著者・日夏梢プロフィール||X(旧Twitter)|Mastodon|YouTube|OFUSE
芸能人の薬物依存疑惑と作家の表現の自由―私論と試論 – こちらでも、メディアの「自主規制」という深刻な問題を論じました。冒頭でまとめたのは、俳優でミュージシャンのピエール瀧が薬物で逮捕された事件です。そのうえで、関係各社の「自主規制」から起こる問題を解説しました。
ハリー王子とメーガン妃の現在と今後―英王室の「失言」に思うこと – 英王室で初のアフリカ系ルーツをもつメーガン妃に対し、王室内で人種差別発言があったと夫妻が告発した事件について書きました。近代において王室の結婚には構造的な無理があるということを指摘しています。
叙勲・褒章、国民栄誉賞とその辞退者―調べてわかった驚きの過去 – 内閣の「助言と承認」により天皇が国事行為として行う栄典授与を解説しました。大日本帝国憲法下での天皇の栄典大権や叙勲も扱っています。
「今年」世に送りたい4つの提言 – 憲法記念日に出した、天皇退位と新元号「令和」についての記事です。