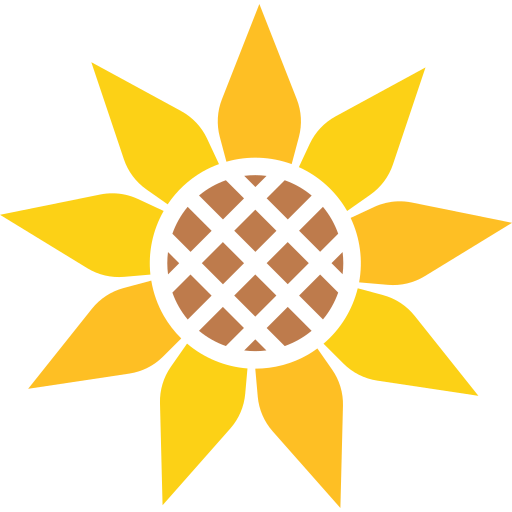『ロケットマン』(原題:Rocketman デクスター・フレッチャー監督、2019年、米・英)は、ブリティッシュ・ロックの大スター、エルトン・ジョンの半生を描いたミュージカル・伝記映画です。
受賞歴と批評家からのレビューが華々しい本作、中身は映画としてそれに値する充実ぶりでした。エルトン・ジョンの楽曲群はもちろん、同じくブリティッシュ・ロックスターQueenを描いた大ヒット作『ボヘミアン・ラプソディ』と深い関連性があり、さらに私は心に深い傷を負った人に自信を持っておすすめできると確信するなど、見方や楽しみ方が豊富です。今回は、そんな見どころいっぱいの映画『ロケットマン』のあらすじをまとめ、レビューや感想などを書いていきたいと思います。(以下、結末までのネタバレを含みます。)
『ロケットマン』あらすじ
真っ赤な悪魔のステージ衣装に身を包んだロックスターが、きらめきながら登場する。エルトン・ジョンだ。しかし彼が向かったのは、コンサートのステージではなく、依存症の集団リハビリセッションだった。彼はアルコール、薬物、性関係、過食、処方薬、そして買い物に依存しており、怒りのコントロールにも問題を抱えているという。カウンセラーから子供時代を尋ねられた彼は、昔の自分を回想し始めた。
のちのエルトン・ジョン、本名レジー・ドワイトは、冷たく不仲な両親のもとで孤独を抱えるシャイな少年だった。家のピアノやレコードを触っては、独りベッドで音楽家になった自分を夢見るレジー。愛情ある祖母・アイヴィの勧めでピアノを習い始めると、先生からこれなら王立音楽院の奨学生になれると背中を押されるまでになる。手を貸さずに突き放す母親・シーラをよそに、アイヴィは彼を音楽院まで送り、緊張する彼を励ました。試験では、聞いたばかりの曲を再現してみせて合格。それ以来、レジーは音楽院の本格的なピアノレッスンに夢中になる。しかし父・スタンリーは家族に無関心で、レジーを邪魔者扱いし、一方のシーラは別の男性・フレッドと浮気。とうとう離婚となる。ハグひとつない冷たい別れに、レジー少年は「愛がほしい」と歌ったのだった。このころから、レジーの心は王立音楽院で習うクラシックから、ロックミュージックに傾倒していく。
数年後、成長したレジーはバンド「ブルーソロジー」のピアニストとして働いていた。アメリカ人ソウルグループの演奏にバックバンドとして参加した際、レジーはカリスマ性ある黒人シンガーに「小太りでメガネと見た目の冴えない自分がどうしたらソウルマンになれるか」と尋ねてみる。彼の答えはまず「曲を書け」と一言。続いて、名前を変えることだった。彼自身、世に知られた名は芸名であり、やせこけた黒人からソウルマンになった。なりたい自分になるために過去の自分を殺すのだ、という。レコード会社のミュージシャン募集広告に応募したレジーは、名を「ブルーソロジー」の仲間から、姓をビートルズのジョン・レノンからとって「エルトン・ジョン」と名乗ったのだった。
面接に出てきたレイは実は上司・ディックの下で働く若手にすぎなかったが、「歌詞に曲をつけてくれ」と期待の目で封筒を渡す。エルトンは、その書き手で作詞家志望のバーニー・トーピンとカフェで面会。カントリー音楽が好きだという共通点もあって意気投合する。ディックはバーニーのほうがルックスがいいからとシンガーの役割を勧めたが、バーニーは声がいいとエルトンを推した。以来、二人は兄弟のようにきずなを深め、20年以上口論したことがないと後に振り返っている。
ディックの意向で二人は同居を始めたが、エルトンが間借り先のガールフレンドにゲイだと打ち明けたことで追い出されてしまう。しかたなくエルトンはバーニーを伴って母親のもとへ帰り、曲を書くことになった。「僕にできるのはこれだけだから歌を贈る」と歌った『Your Song』を、ディックは『Let It Be』以来の名曲だと絶賛。1年間でアルバム3枚を出し、アメリカの有名クラブで演奏だ、と大きな賭けを組み、自信なさげなエルトンに「自分を見せつけてこい」と送り出す。ニール・ヤングが歌い、ボブ・ディランが出入りし、他にも数々のアメリカン・ロックスターが出演するロサンゼルスの有名クラブ「トルバドール」でエルトンは『Crocodile Rock』を絶唱。アメリカデビューは大成功を収めた。
その夜のパーティーは祝勝会のようだった。バーニーは夢が叶ったと喜び、新しいガールフレンドを見つけたのだが、エルトンはその背中をさびしそうな目で見つめていた。そこで高級な酒を手に近づいてきたのが、音楽マネージャーのジョン・リードだ。リードは「曲よりも人がいい」「君は誰にでもなれる」と甘い言葉でエルトンの孤独な心をつかみ、二人は恋人同士になった。
一行はロンドンに帰り、新曲を調子よくレコーディングしていると、リードが突然訪ねてくる。彼から「上を目指せ」とたきつけられたのをきっかけに、エルトンの生活は、食事とアルコールにふけり、名画を買いあさり、豪邸を買うなどと派手になっていった。やがてリードは専属マネージャーになると提案。それまでよき理解者であり、親身にマネジメントしていたレイと、その上司ディックを追い出す形になる。立場を固めたリードは、「マスコミに二人の関係がバレないよう両親と口裏合わせしてこい」と言い渡したのを皮切りに、エルトンに対して支配的な態度をとるようになっていった。
エルトンが片耳だけイヤリングをして(注:同性愛を表す)スタンリーを訪ねると、彼は再婚して幼い息子二人の父になっていた。表面的には出迎えるものの、音楽には関心を示さず、レコードへのサインを自分宛てにするのを拒むスタンリー。エルトンの去り際には、かつて彼には決してしなかったように息子を抱き上げ、楽しそうに家へ入っていった。エルトンは悲しみと怒りで取り乱し、母シーラには公衆電話から同性愛を告白。するとシーラは、彼の同性愛には何年も前から気付いていたが、黙っていてほしいと言いつけると、「あなたは一生愛されない」と告げて電話を切ったのだった。
エルトンの人気は破竹の勢いだったが、楽屋で鏡に映る表情には憔悴が表れていた。無理やり笑顔を作る彼に、バーニーは、本当にこんな衣装で歌いたいのか、「レジー」に戻ってもいいんだ、と切り出す。しかしエルトンは「兄弟」の助言をはねつけ、ステージではきらびやかな衣装を次々変えて「エルトン・ジョン」を演じきった。
疲れ果て、自宅豪邸のベッドに伏せていたエルトンは、リードにしばらく二人で静かに暮らさないかと声をかける。が、そこで目の当たりにしたのは、秘書と浮気をするリードの姿だった。二人の恋愛関係は終わりを告げる。だが、契約によってビジネス上の関係は切れることなく、しかもリードにはエルトンの死後も利益の2割が入るようになっていた。自宅で盛大なパーティーが行われているにもかかわらず、ベッドルームでひとり飲酒にふけるエルトン。バーニーが誘いに来ても「僕がいなくても誰も気にしない」といじけた態度をとる。ついには処方薬を大量摂取し、「ショー」だと叫んで庭のプールに投身。もうろうとする意識の中で、「宇宙は孤独だ、昔に戻りたい」「地上に戻って気が付くまでは長くかかるだろう、自分はみんなが思っているような人じゃない」と、自分の本心に出会ったのだった。エルトンは周りの人々に引き上げられたが、リードは担架で運ばれゆく彼に「自分勝手な」と冷酷な非難を突き付けた。
バーニーからの、身を隠し、昔のように曲を作ってやり直そう、という提案は蹴ってしまい、観客への態度が悪化したのと呼応するかのように曲の売り上げも落ち目に。そんな折、エルトンはスタジオでレコーディングエンジニアの女性・レネーテと出会う。楽曲を「正直で、嘘がないから好き」とよく理解し、「チャンスをつかんで生き方を変えて」と優しく接する彼女は新しい希望となった。二人は結婚。式には母親も参列したのだが、同性愛者のエルトンが女性と幸せな関係になれるはずもなく、結婚生活はあっという間に破綻した。
傷心のエルトンに、シーラとフレッドは外国の島に家を買うからと言って金をせびる。外国に引っ越さなければならないのはエルトンがスキャンダルを振りまくせいで苦労を強いられているからだ、という。エルトンは悲痛につぶやいた。「あんたに心はない」と。するとシーラは、お前はピアノに出会ってから運良くかんたんに成功したが、自分はいつも犠牲になっていて、お前が生まれていなければよかった、お前の母親であることにどれほど失望させられているかと、涙を浮かべながら非難を浴びせたのだった。
バーニーが戻ってくるが、エルトンの悲しみと屈折は極度に達していた。あの祝勝会の夜、一番いてほしい時にガールフレンドを選んで自分を棄てたじゃないか、自分は四六時中働いてスターとして今では外も歩けないが、君は裏で歌詞を書いているだけだ、などと愛を試すような言葉をぶつけると、バーニーは怒って出て行ってしまう。
「兄弟」まで裏切ったと、過食、薬物、アルコールにおぼれていくエルトン。倒れて病院に運ばれるが、リードはその程度なら平気だと公演を追加した。楽屋には入ったものの、顔色は悪く、ステージ向けの表情を作ることもできない。とうとう意を決したエルトンは、きらびやかなステージ衣装を着たまま公演をけって、依存症のリハビリ施設に向かったのだった。
エルトンは心の中で、これまでに彼を傷つけた人々と対峙する。「お前は自分勝手なのが問題だ」と責めるリードには、お前の愛を信じたのが間違いだった、と。「お前は変だ」となじる父には、それでいい、と。口論を始める両親には、やめろ、そして、今後自分への侮辱は許さない、と。長年の呪縛をついに突き放したエルトンは、孤独な少年時代の自分に「レジー・ドワイト」は大昔の自分だと答え、しかと抱きしめたのだった。
郊外のリハビリ施設にバーニーが訪ねてくる。そして出会ったころを思い出させるかのように、歌詞が入った封筒を置いていった。エルトンは「ありがとう」と素直に感謝を伝えると、音楽セラピー室でピアノに着く。「僕はまだ立っている かつてない強さで 真の生還者のように 無垢な子供のように すべてを乗り越えて お前なんて忘れて」と。
後、エルトンは、買い物に問題を残しているものの禁酒に成功。バーニーとは音楽活動のよきパートナーであり続け、夫と二人の子と暮らしている。長年の困難を乗り越え、本当の愛を手に入れたのである。
レビューと感想―ロックと美と現実性のアレンジメント
私はロックミュージックへの関心から『ロケットマン』に手を伸ばしたのですが、見終わってみると良い意味で予想と違った作品でした。
実はその本作、同じくブリティッシュ・ロックスターの生涯を描いた『ボヘミアン・ラプソディ』で最終監督(無断欠席を理由に解雇されたシンガー監督の代行)を務めたフレッチャー監督がメガホンをとっています。しかも、共通して登場する人までいるんですよ。映像美術の見比べ、音楽の聴き比べと、私はいろいろな楽しみ方を満喫しました。以下では、『ロケットマン』のレビューや感想に加え、比較によって思わずニヤリとするポイントなどを書いてみたいと思います。
特筆すべき音楽シーンのパート分担
私はこれまで数々のミュージカル映画について書いてきましたが、『ロケットマン』の音楽シーンには特筆すべき点がありました。それは、使用楽曲がエルトン・ジョンの既存楽曲であるにもかかわらず、登場人物らに歌詞を割り振ることで、それぞれの心情を見事に描き出した点です。音楽を使った表現にはこういう手もあるのかと開眼した気分でした。
パートを分担して歌われるのは
- I Want Love
- Honky Cat
- Rocket Man
- Don’t Let the Sun Go Down on Me
- Sorry Seems to Be the Hardest Word
- Goodbye Yellow Brick Road
の6曲。本作のための書き下ろしではないかと疑ってしまうほどのハマりぶりでした。
いきなり核心を突く『I Want Love』
私は序盤、『I Want Love』でいきなり舌を巻きました。この作品はアンサンブルへのアレンジとパート分担によってこう見せてくるのか、と。
少年レジーが「愛がほしい」と歌うのは分かりますが、巧みなのはその後です。あのひからびたような父親は「普通の男性はもっと自由だが、自分は心が死んでいるようで人を愛せない」、夫に愛想を尽かした母親は「縛り付けるのとは違う、別の愛がほしい」、そして、夫婦の不仲とレジーの悲しみを目の当たりにしてきた祖母は「すれ違う人を見すぎて、私は重荷を背負いすぎている」。そうだろうな、とそれぞれに納得でした。これが書き下ろしでなく、エルトン・ジョンが単独で歌う既成楽曲だというのが驚きです。
心理分析は『I Want Love』の時点で出し尽くしたに近いといえるでしょう。後から戻って、何度でも聴きたくなります。
表題『Rocket Man』の美麗な宇宙遊泳
私は『I Want Love』の時点で「これは」と思っていたのですが、タイトルロール『Rocket Man』のシーンはまた格別でした。
プールの暗い水底が『Rocket Man』の孤独な宇宙と重ねられ、夢見る子ども時代の自分と出会うあのシーンは一度見たら忘れられません。独創的な象徴です。
しかも、歌詞では暗い宇宙から「長い時間がかかるだろうけど地上に戻りたい」と歌っているのに、プールに沈んだエルトンは暗い底から光差す明るい水面を見上げている。音楽と映像で上下のベクトルが反対になっているところに、芸術的な美を感じます。
エルトンを助けに飛び込んでくる人々の服がなびく様もまた幻想的。宇宙遊泳のようなイメージが重なる美麗なシーンでした。
悲しすぎる悲しみ分析
ひどい……いくらなんでもひどすぎるよシーラお母さん……。
突然島に別荘を買うと言い出して、スターになった息子に当然のごとく金をせびり、挙句の果てに自分は彼のせいでそうせざるを得なくなった犠牲者であって、あんたなんて生まれなければよかったのに、と、頭のネジがふっとんだトンデモ論理を振りかざす。息子の心をズタズタに引き裂いておいて、自分が犠牲者だと主張する――。
開いた口がふさがりませんが、見ているこちらとしては、この人はどうしてこんなダメ人間になってしまったのか、そろそろ首をかしげる頃なんですよね。
なぜシーラお母さんはああなのか、エルトンの答えは『Sorry Seems to Be the Hardest Word』。
思うに、謝れないんだろう。今さら……。
この親子は、この病んだ関係性で定着してしまっているんですよね。親子関係がシステムとしてああだから、そのシステムの一部であるシーラが変わることはない。いつまでも同じパターンでエルトンの存在を否定し、虐待し続ける――。
「被害・加害関係が逆に語られる」というのは、親による子の虐待では頻繁に見られる心理学的現象です。信じられないかもしれませんが、めずらしい話ではありません。被害・加害の逆転が日常化し、当たり前の前提として語られているシステムでは、内部者が内側からそれを破るのは至難の業。乗り越えるのに「長くかかる」ケースを、現実に即して、よく描けていたと思います。
『ボヘミアン・ラプソディ』との見比べを楽しむ
『ロケットマン』を観ながら私が頭の中で興じていたのは、Queenのフレディ・マーキュリーを描いた『ボヘミアン・ラプソディ』との見比べです。監督が同じで、登場人物も一部共通。別個の作品とは思えないほど関連性が深いのです。
参考:映画『ボヘミアン・ラプソディ』あらすじと感想―クイーンの新たなロック伝説!(新しいタブで開きます)
封切りは『ロケットマン』のが後ですが、ストーリーの時系列ではやや前になりますね。……こうやって事実関係をチキチキ整理するだけで、私はけっこうニヤニヤしました。
無論、両作はどちらも独立した作品です。なので比較するのはやや失礼だとは承知なのですが、私は表現方法の方向性の違いなどにも注目して楽しみ、いろいろ考えたりしました。
音楽シーンの違い
両作品の違いを探していくと、まず楽曲の使い方が挙げられます。
『ボヘミアン・ラプソディ』は、シーンに合ったQueenの楽曲をバックに流すことで物語をつむいでいく形式でした。キャストが歌うわけではなく、ダンスシーンもなし。ミュージカルではなく、あくまで一般の実写ドラマ作品です。
一方、『ロケットマン』はもっとミュージカル仕立て。ストーリー中の歌唱はすべてキャストで、ミュージカル形式のダンスシーンもあります。たとえばレジーのバックバンド時代や、リードの手引きで派手な浪費生活に入っていくところは歌とダンスによって描かれていますね。表題『Rocket Man』の水中シーンに代表されるように、音楽シーンでは象徴的な表現が多用されています。
ドラマとしてクリアな筋立てが魅力的な『ボヘミアン・ラプソディ』に対して、『ロケットマン』はもう少し映像美術志向という感じでした。
まさかのあぶない男、ジョン・リード!
黒スーツでビシッとキメ、甘い言葉でエルトンの孤独な心に忍び込み、さんざん言い寄ってアルコールや薬物の道に引きずり込み、金をむしり取るため支配下に置いていく――そんな「あぶない男」のジョン・リード、実はQueenのマネージャーとして『ボヘミアン・ラプソディ』にも登場します。20世紀のブリティッシュ・ロック。同時代の同分野を描いたゆえですね。
ですが、こちらでのリードはとりたてて目立たない、ごくまともなマネージャーなんですよ。まだ学生バンドの延長にすぎなかったQueenの前に「かのエルトン・ジョンをマネジメントした人物」として現れ……その後の詳しい話はネタバレになってしまうので『ボヘミアン・ラプソディ』の記事を参照してもらいたいのですが、ロックスターに言い寄って支配するとか、金もうけのため無理に働かせるとか、そういう人間性は少しも出てきません。
だから私は『ロケットマン』でのリードに「アレ!?」と目玉が飛び出しました。「ジョン・リードってこういう人だったの?」と印象がひっくり返ったのは、きっと私だけではないと思います。
彼の別の一面を見てしまった、というだけではありません。というのも、『ボヘミアン・ラプソディ』には、ジョン・リードではない別の「あぶない男」が出てくるんですよ。これも詳しくはネタバレになってしまうのでそちらを読んでもらいたいのですが……何、こういう「あぶない男」ってブリティッシュ・ロックにつきものなの!?
新しい世界というか、自分には見たことのなかった人間模様を目の当たりにして、私の心には何とも形容しがたい感慨が残りました。それは「文化の違い」というほど深刻ではない、偶然と社会的背景が折り重なって、その時代、その分野に自然発生したカルチャーといいましょうか。ある社会において人の性格、言動、人間関係の典型パターンが発生する過程を目撃したようで、人間への洞察がちょっぴり深まった気がします。
リハビリシーンの象徴と写実の優秀さ
私が『ロケットマン』という作品で非常に高く評価しているのは、リハビリで傷つけられた過去と向き合っていく過程が非常に現実的に描かれている点です。「情報」として適切なので、同じような心の傷を抱える人に自信を持っておすすめできますし、できれば教えてあげたいなと思っています。それが本作をブログで扱おうと思った理由の一つでもあります。
その写実性は、映像向きな象徴表現と二重らせんのようにうまくからみ合っていました。スパンコールにツノに羽と、いくらなんでも作りすぎなロックスターの衣装を少しずつ脱いでいく――「本当の自分」になっていく様子が目で見て分かりやすく、説得力がありますね。
被虐待体験はこうやって乗り越える
と、衣装の部分は象徴的ですが、リハビリの中身は非常に現実的です。
エルトンは最初「父親は家族想いで、何時間も音楽を語り、ハグしてくれて、幸せな子どもだったよ」と事実を美化した話から入るので、「えっ、なんで」と狐をつままれたようになった人もいることでしょう。が、この行動パターンが物語るのは、日常離れした傷の深さです。回想が進んでいくと、心の底に抑圧されていた辛さと悲しみが目からぼろぼろこぼれ落ち、怒りが噴出して、すべてを吐き出し、その果てに本当の自分と向き合い、ついに虐待をはねつける――これはエルトン・ジョンだけでなく、世界中の虐待されていた人が通っている道です。
私がとりわけ高く評価するのは、リハビリの最後を「作者にとって理想的な結末」に結びつけなかったことです。世の中には「こうして被害者と加害者は互いを分かり合い、まあるく収まったのでした」と美談のハッピーエンドにしようとする作家は少なくないのですが、これは「情報」として毒性が強く、社会的には問題があります。被虐待者の受けてきた不当かつ言語道断な苦しみが、最後の最後で相対的に小さく見せられてしまうからです。「手を取り合うのが美しい」というのは、作者の身勝手な理想にすぎません。結果的には、第三者の苦しみを自分の作品に利用した挙句、本人および不特定多数の被虐待者にさらなる精神的抑圧を強いてしまう。その点、『ロケットマン』は、虐待的扱いをした人々にノーを突き付けることでエルトンが自己の尊厳を回復する様を、現実に即して、適切に描写できていました。
エルトンが子どもの頃の自分を抱きしめるシーンは、何度見ても涙がこみあげてきます。そう、乗り越えるとはこういうことなんです。
「ミュージシャンの伝記」というトレンドに一言
近年映画界のトレンドとなっている「実在ミュージシャンの伝記」。これだけヒット作、優れた作品が生まれているのですから、「うちもやろう!」という波ができるのは自然な成り行きかもしれません。
しかし、私はこの傾向に一本くぎを刺しておきたいとは思っています。伝記(評伝)というカテゴリに内在する難しさを、我も我もとなだれ込む映画やドラマの制作者はきちんと意識できているのか、と。
批評家のレビューで高評価を得ている『ロケットマン』ですが、創作意図は、と問うたらどうでしょうか。「フレッチャー監督の作品」とみるべきか、それともエルトン・ジョンに関する企画作品、あるいはもっと抽象的にロックスターの浮き沈みを描いた一般作の扱い……作品の趣旨はどれとも言い切れず、映画一般と比べてぼんやりしています。私は見る側として、スクリーンに対してどんなスタンスをとるかは決めにくいなと感じました。
また、伝記の題材として「ミュージシャン」は微妙な職業だという点に関しては『ボヘミアン・ラプソディ』の記事ですでに指摘しました。良い作品にまとめ上げるのはそうかんたんではありません。
「自伝」が失敗しやすい理由
また、本作はエルトン・ジョン本人が制作総指揮として参加しているのですが、この体制には一か八かというところがあります。
なぜなら、「自伝」は数ある表現形式の中で指折りに失敗しやすいカテゴリだから。自分のことを自分で語るゆえ、主観的になりやすいのです。実際、自伝の多くは、ただの自慢話や宣伝広告、あるいは誰かへの恨みを書きなぐったものだったりする。あなたにも「そんなの見た見た!」と思い出される本などがあるかもしれません。
『ロケットマン』で描かれる自己分析は深く、十分な域まで客観化されています。本人しか知らない事実まで確認をとれるなら、吉と出る。しかし凶と出れば、世人のせせら笑いを買う「トンデモ本」や「イタイ人」で終わりです。
きな臭い商業主義に陥らないためのお手本として
私は『ロケットマン』は優れた映画だったと評していますし、それと関連の深い『ボヘミアン・ラプソディ』も少し違う方向でヒットに値する作品だったと思いますが、ミュージシャンの伝記を作れば必ずしもこのように成功できるというわけではありません。もし作品のクオリティを上げきれなければ、有名人をダシに話題を振りまく、きな臭い商業主義にすぎないのです。
伝記(評伝)というのは、フィクションと事実との境目があいまいな、微妙な分野です。失敗しやすく、社会的に好ましからざるものになりやすい。もっと行けば、ある人物に関する事実のねつ造に悪用されることもあります。
だから、ヒット作に目を輝かせて「それ行け!」とばかりに安易に手を出してはほしくない。映画制作者には、もしミュージシャンの伝記に取り組むのであれば、本人の作品への尊重、芸術性、社会的な適切さを兼ね備えた、『ロケットマン』と同水準の作品を目指してほしいと思います。
関連記事・リンク
著者・日夏梢プロフィール||X(旧Twitter)|Mastodon|YouTube|OFUSE
映画『ボヘミアン・ラプソディ』あらすじと感想―クイーンの新たなロック伝説! – ブリティッシュ・ロックの伝説的バンド・Queenのリードボーカル、フレディ・マーキュリーの伝記映画で、時代はもう少し後、1970年代から始まります。『ロケットマン』とは別人のジョン・リードと、別の「あぶない男」が見られます。
『グレイテスト・ショーマン』あらすじと感想―現代に響く人間賛歌 – 私にとって評価と好みが一致したイチオシのミュージカル映画。この作品も「なりたい自分」がテーマです。
『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』あらすじ(ネタバレ有)&感想―衰え知らずの圧巻手腕 – ジェームズ・キャメロン監督のSF大作。本作で印象的だった水中の映像表現が、最新の技術により、全体を通して圧巻の映像美を生み出しています。
評価二分の『ONE PIECE FILM RED』~ウタはなぜ”炎上”したのか – 近年の流行を受けて音楽映画に着手したものの、クオリティを上げきれず、出来の面で失敗した例だと思われる作品です。原作は人気マンガ『ワンピース』ですが、私の指摘のほとんどは原作ストーリーやキャラクターとは関係ないので、音楽映画論としてよろしければ目を通してみてください。