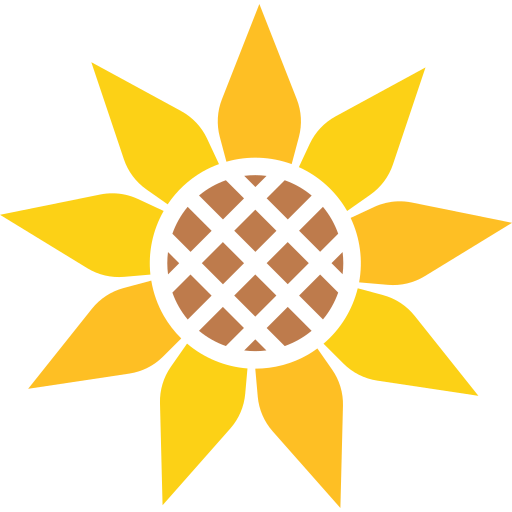『レ・ミゼラブル』(原題:Les Misérables トム・フーパ―監督)は、2012年に公開されたミュージカル映画。原作はヴィクトル・ユゴーの同名小説で、本作はそのミュージカル版の映画化となります。本稿では、その詳細なあらすじと、原作小説との比較も含めたレビュー、そして私の感想を書きました。(以下、結末までのネタバレを含みます。)
レ・ミゼラブル あらすじ
1815年
大革命から26年。フランスでは王政(注:フランス革命以前のブルボン王朝)が復古していた。
ジャン・ヴァルジャンは、パンを1つ盗んだ罪で服役している徒刑囚だ。19年も鎖につながれ奴隷労働に従事していた彼は、ついに看守・ジャヴェールから仮釈放の許可証を渡されて出獄する。自由を信じたジャン。しかし、許可証に「危険人物」との記載があるため仕事にはありつけず、行く先々で人々から怪しまれ、泊めてくれる宿もないのが現実だった。
ところがある夜、あたたかく招いてくれる人が現れた。土地の司教・ミリエルだ。汚い風貌でせっかくの夕食も粗野にかき込むジャンだったが、ミリエルは普通の人と同じように丁寧に接したのである。ジャンは戸惑いながらも、家が寝静まってから銀の食器を盗んで逃走。しかし翌朝、憲兵に捕まり、司教のもとに連れてこられる。またあの徒刑場に戻るのか、と恐怖に凍りつくジャン。その時、ミリエル司教は、銀の食器は彼があげたものであり、それより上等な銀の燭台は朝早くに出発したのでうっかり忘れてしまったのでしょう、と説明して、憲兵を帰らせた。盗みを見逃してくれたのだ。ミリエル司教は、銀を正直者になるために使うようにと約束してジャンを送り出す。生まれて初めて人の優しさに触れ、信頼してもらったジャン・ヴァルジャンは、仮出所証を破り捨て、生まれ変わると決意したのだった。
1823年
モントルイユという田舎町は、人格者として誉れ高く、工場の経営者でもあるマドレーヌ市長のもと、貧しいなりに繁栄していた。このマドレーヌ市長こそ、名と素性を隠したジャン・ヴァルジャンだ。
工場で働く労働者のなかに、ファンティーヌという若く貧しい女工がいた。ある時、ファンティーヌは届いた手紙を他の女工に見られたことから、隠し子がいることがばれてしまう。マドレーヌ市長は騒ぎを止めに入るが、モントルイユに着任したばかりのジャヴェール警部の視線を感じたため、工場長にその場を任せて去ってしまった。ファンティーヌに男がいたと知ってへそを曲げた工場長は、彼女を解雇。仕事を失った一方で、娘・コゼットの預け先であるテナルディエ夫婦に借金があるファンティーヌは、髪を売り、歯を売り、ついには売春婦に身を落としたのだった。
そんなある夜、金持ちの遊び人・バマタボワとトラブルになったファンティーヌはジャヴェール警部に突き出される。牢獄に送られたら娘がどうなるのか、と慈悲を懇願するファンティーヌ。そこに現れたマドレーヌ市長ことジャン・ヴァルジャンは、自分のせいでファンティーヌが生き地獄に落ちたと知ると、彼女を牢獄ではなく病院に送り、さらにはコゼットを呼び寄せると請け負ったのだった。
ジャヴェール警部はモントルイユに着任以来、マドレーヌ市長が徒刑囚ジャン・ヴァルジャンではないかと疑い続けていた。マドレーヌ市長が馬車の下敷きになった老人・フォーシュルヴァンを助け出した様子を目撃し、その怪力から徒刑囚ジャン・ヴァルジャンを思い起こしたからだ。そんな折、パリから報が入る。本物のジャン・ヴァルジャンが捕まったというのだ。マドレーヌ市長は青ざめ、葛藤に陥る。自分と勘違いされた無実の男をこのまま徒刑場に送るわけにはいかない。しかし、苦労して手に入れた地位を捨てて奴隷状態に戻ることは受け入れがたいし、今や彼の工場経営には何百人もの労働者たちの生活がかかっている。しかし、正直者として生きると決めたジャンは、嘘を通すことはできなかった。裁判所へ赴き、自分こそ本物のジャン・ヴァルジャンだと名乗り出て、無実の男を救ったのだった。
モントルイユに急ぎ戻ったマドレーヌ市長は、コゼットを大事に守り育てると約束して、病床のファンティーヌを看取った。そこへジャヴェール警部が登場。ジャンはコゼットのために逮捕を3日待ってくれと頼むが、法と規則に従うことに全身全霊をかけ、「犯罪者は決して変わらない」と信じるジャヴェールはまったく信用しない。決闘になったジャン・ヴァルジャンは、川に飛び込んで逃走した。
テナルディエ夫妻は、モンフェルメイユという村で宿屋兼安料理屋を営むうさんくさい夫婦だ。エポニーヌというコゼットと同じ年ごろの娘を猫かわいがりする一方、コゼットを召使いとしてこき使っていた。
クリスマスの夜、コゼットは夜の森へ一人で水をくみに行かされる。そこで出会ったのがジャン・ヴァルジャンだ。彼はテナルディエに、借金を払ったうえでコゼットを引き取ると申し出る。テナルディエ夫婦はコゼットを金づるにしようとなかなか手放さないが、ジャンは過大な請求をうまくまとめた。ジャンにとってコゼットは生まれて初めて愛しく思える相手で、コゼットにとってジャンは優しい父親となった。言えない過去と危険を伴う先行きに不安を抱えながらも、ジャン・ヴァルジャンはコゼットを連れてパリへ出ていった。
パリでは、逃走したジャン・ヴァルジャンをとらえるため、ジャヴェール警部が厳しい検問をしいていた。ジャンが決死の逃避行で逃げ込んだ先は、女子修道院で、そこではかつてモントルイユで命を助けたフォーシュルヴァンが働いていた。侵入者が「マドレーヌ市長」だと分かり、フォーシュルヴァンは恩返しを申し出る。こうしてジャン・ヴァルジャンは安全な隠れ家を得て、コゼットとともに新しい人生を始めるのであった。そのころ、またしてもジャン・ヴァルジャンをとり逃がしたジャヴェールは、たゆむことなく追い続け、必ずとらえると星空に誓うのだった。
1832年
時は経ち、七月王政(注:1830年、ブルボン王朝を倒した七月革命で新たに即位した、オルレアン公ルイ・フィリップの王政)下のパリ。学生を中心とした民衆の間では、革命の機運が高まっていた。
マリウスは、金持ちの祖父と縁を切り、あばら家に住んでいる革命家の青年だ。同じパリでは、落ちぶれて犯罪者となったテナルディエ夫妻や、マリウスに心を寄せるエポニーヌ、親切な紳士とその娘――ジャン・ヴァルジャンと成長したコゼットだ――や、革命運動のリーダー・アンジョルラスと仲間たち、明るく生きる浮浪児のガヴローシュなど、様々な人が暮らしている。アンジョルラスは、民衆寄りの姿勢が名高いラマルク将軍の死をきっかけに決起を決めた。そんな激動の中出会ったコゼットとマリウスは恋に落ち、ひそかに愛を育てていく。
革命前夜。いよいよジャヴェールに居場所がばれたと考えたジャンは、コゼットを連れてイギリスへ引っ越すことに決める。コゼットは突然の話に驚き、父親が謎だらけで本当のことを話してくれないと、初めてジャンに反発した。コゼットからの置き手紙を読んだマリウスは、愛を誓った彼女と別れ別れになったら生きていけないと絶望に打ちひしがれ、葛藤の末、仲間たちが起こす革命への参加を決意するのだった。
ラマルク将軍の葬儀が始まると、パリの民衆は蜂起。抑圧を制し、王政を倒して民主主義を勝ち取るため、バリケードを築いた。
その夜、バリケードが急襲されるが、マリウスは自分もろとも火薬を爆発させると脅して警察を退避させ、危機を救う。だが、その戦闘でマリウスをかばったエポニーヌは犠牲となった。マリウスはコゼットへの手紙をガヴローシュに届けさせるが、戸口に出て受け取ったのはジャン・ヴァルジャンだった。コゼットのひそかな恋を知って衝撃を受けるジャン。革命に参加しつつもコゼットのために生き延びたいというマリウス。ジャン・ヴァルジャンは、コゼットが恋する若者を探すためにバリケードへ向かう。そこでは、革命勢力のスパイをしていたジャヴェールがとらえられていた。ジャンにとって、ジャヴェールはかつて自分を酷使した敵であり、生涯の脅威であるはずだ。これを好機に始末する、と思いきや、ジャンは空の発砲で処刑を偽り、彼の命を救う。のみならず、自分の住所さえも教えて、宿敵をバリケードから逃がしたのであった。
バリケードに集う面々は革命成功を信じていた。だが、パリの民衆はついてこない。孤立して勝ち目はなく、バリケードの希望はついえた。しかし彼らは、たとえ自分たちが倒れようとも、地上には後に自由のため戦う者がいるからと、戦い抜くことを選んだ。朝の戦闘でマリウスの仲間たちは次々と死んでいき、バリケードはついに陥落。参加者はみな死亡した。
戦闘のさなか、ジャン・ヴァルジャンは意識不明重体のマリウスを背負い、下水道へ逃げ込んでいた。命がけで汚物の泥沼から抜けたのだが、それもつかの間、出口ではジャヴェール警部が待ち構えていた。ところがジャヴェールは、彼らしくもなく、ジャンを撃つことができない。「犯罪者は悪事しかしない」という極端な考えのジャヴェールは、逃亡中の徒刑囚でありながら憎き敵に慈れみをかけ、命がけで人を救うジャン・ヴァルジャンを理解できなかったのだ。生まれて初めて迷いを抱き、自身の世界観が崩れ、心の行き場を失ったジャヴェールは、川に身を投げて自殺した。
マリウスはコゼットと再会した。その時ジャン・ヴァルジャンは、マリウスだけに、仮釈放中の徒刑囚で逃亡している身だという自身の真実を告げる。マリウスはコゼットに説明しようがないからと言って止めるが、ジャンは遠くへ旅に出るということにして、最愛の娘を置いて去った。
やがてコゼットとマリウスは結婚。華やかな結婚式には、テナルディエ夫婦が潜り込んでいた。マリウスはテナルディエから、自分をバリケードから救い出したのがジャン・ヴァルジャンであること、彼の居場所が修道院であることを聞き出す。マリウスとコゼットは結婚式のその足で修道院に急行、死の際にあるジャン・ヴァルジャンのもとへ駆けつける。マリウスはジャンにこの上ない感謝を伝え、ジャンは真実をつづった手紙をコゼットに残した。ジャン・ヴァルジャンは、若い二人の愛を永遠のものにして苦難に満ちた生涯を終え、この世を去ったのであった。
レビュー:物語の「ツボ」をすべて押さえた傑作!
ヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』は歴史上何度も舞台化・映画化などをされてきた作品ですが、本ミュージカル映画はその趣旨・要点を余すことなく押さえたすばらしい出来でした。文章と比べて伝えられる情報量が少ない「映像」という表現方法でよくここまで、というくらい見事です。
一つの映画作品としてよくまとまり、完成度が高いため、見終わった後の満足度が高い一作でした。
登場人物それぞれの素性と思想
なんといっても、本作は主要人物の素性や思想をくまなく描き出しているところにクオリティの高さが光ります。いちいち書き連ねたらきりがないので、ここでは重要だと思われる部分だけ紹介します。
ジャン・ヴァルジャンの知られざる過去
『レ・ミゼラブル』を全然知らない人でも、「パンを一切れ盗んだ罪で19年も服役していた男」といえばなんとなく聞き覚えがあったりする――それほど有名なジャン・ヴァルジャンですが、実はもとの懲役刑は5年で、残りの14年は脱獄によって加えられたものだということは、あまり知られていないのではないでしょうか。
冒頭に出てくる徒刑囚・ジャン・ヴァルジャンは、世の中への恨みつらみを煮えたぎらせています。善良な素質がどこかには眠っているにせよ、この時点では脱獄歴まである荒々しい人物なのです。そして、危険人物として信用されないことが、さらなる憎しみにつながっていく。奴隷的苦役が人を荒々しく変えてしまうことを、原作者・ユゴーは冷静に見つめているのです。映画の冒頭でジャヴェールが脱獄に言及した時、私は「おっ、これをとばさなかったのか」と期待を高めました。
ファンティーヌの正しいイメージ
男に棄てられ恋が終わり、とうとう売春婦になってしまった――その素性から、道楽好きな女だったかのように描写されることもあるファンティーヌ。ですが実は、恋多き色気自慢の女などではなく、どん底生まれで教育は受けていないけれど、善良でごく普通の人だというところが物語のミソなのです。たまに翻訳などでファンティーヌのけばけばしい描かれ方が気になることがあるのですが、本作はバランスよく描けていました。
ジャヴェール警部とストーリーの骨格
冷酷一徹、法と規則が命のジャヴェール警部も、ジャン・ヴァルジャンに負けず劣らずどん底出身。本作では彼の生い立ちについて、直接の言及がありました。その名も『The Confrontation(邦題:対決)』という曲で、『レ・ミゼラブル』の骨格たる対立構造が明確に示されています。
演技と歌唱もよかった。犯罪者を執拗に追って追い詰めることに一種の陶酔があり、ある意味高潔でもあるジャヴェールの精神性がよく伝わってきました。
映画オリジナルの工場長は、隠れた名キャラ!
ファンティーヌに男がいたと知って追い出してしまう、女好きでろくでなしの工場長。じつは彼、ユゴーの原作小説には出てこない、ミュージカル版オリジナルの登場人物です。登場は一回ぽっきりのキャラクターでありながら、私は話をスッキリさせるのに一役買っていると感心しました。
というのも、原作小説での展開は、ファンティーヌは宗教道徳のために段階的に追いやられていくというものなんですよ。当時の西洋キリスト教文化圏では、未婚の母親や婚外子に対するひどい差別がありました。「神のもとで愛を誓った結婚は祝福されている。その夫婦の子は神に祝福されて生まれた子だ」というキリスト教の結婚観が、教会で結婚式を挙げていないカップルや婚外子は「神に祝福された世界」の「外」に落ちた人だという差別意識につながったのです。その差別は苛烈を極め、当時の西洋社会で婚外子はもはや人間ではない、奴隷や怪物並みの残酷な扱いを受けていました。『レ・ミゼラブル』のファンティーヌとコゼットがピンチにあるのはこのためです。
ところがその西洋で、こうした差別はここ数十年ですっかりすたれました。今時、西洋人でもそんな結婚観は現実的でないのです。ましてや文化の違いまで挟まってしまえば、もうなんのことやら。19世紀のフランス社会はそうでした、と、距離を置いて見るしかない。私をはじめ一般的な日本人からすればファンティーヌのエピソードは「学問の対象」になりますが、それでは映画を楽しむムードではなくなってしまいますよね。
このように現代には通用しないエピソードを、なんとこのしょうもない工場長が一発解決! 女好きでファンティーヌに言い寄っていたから男がいたと分かってへそを曲げたんだ、という納得のエピソードによって時代や文化的背景の説明を不要にし、誰にでもわかりやすい形でストーリーを先に進めてくれたのです。こんな「適材」を作り出した制作者の巧みさに、私は思わずにやけてしまいました。
音楽・美術のダイナミックさ
この記事で何度も繰り返しますが、本作は「ミュージカル」の「映画」だからこそ完成した作品といえるでしょう。
この情熱的な作風は、どこからくるのでしょうか?
歌唱という表現方法は躍動感を伴うので、『レ・ミゼラブル』の劇的なストーリーとは相性がいいとみえました。そして歌詞とメロディでは、始終、別の人物によって同じフレーズがリフレインされていきます。寄せては返し、返しては寄せる波のごときダイナミックさ! 理路整然とした構造が名高く、あらすじ的には古い世代のバトンが若者へ渡されていく本作によくマッチしています。
美術面でも、映画だから表現できた壮大さが光りました。ラマルク将軍の葬儀から暴動、革命が始まる場面は、革命の参加者が無数に映ることで映画としては迫力が、物語としては説得力が増したのがうれしかったですね。エンディングのバリケードは、空撮によるスケール感で開放的な感動があふれました。
ダイナミックでパワフルな作風は、「ミュージカル映画」だからできたと言っていいと思います。
感想―「人々の声が聞こえてくる」
人権保障がないとは、こういうこと
「映画」であるメリットが光った作品だ、というのが私の第一印象でした。なので感想を文字で書いたらどこまで伝わるのかなとは思うのですが、とりあえず語らせてください。
冒頭はいきなりショッキングです。主人公が首輪をはめられ、鎖につながれ、名前ではなく番号で呼ばれている――目を覆いたくなる最悪なシーンですが、これは架空の話ではなく、19世紀のフランス社会の現実をそのまま使用したものです。
今日、私たちは人権保障や民主主義があって当たり前の世の中に生きています。人が首輪をはめられ鎖につながれるなんて、私たちにとってはスクリーンの中のお話。
ところが近年、人権保障や民主主義がある国家・社会で腐敗が増えています。憲法による人権保障があっても、この社会は生きにくい。アメリカ人は、あんな明らかに危ないトランプさんを大統領に選んでしまった。日本は汚職につぐ汚職で、まともな民主主義国家かどうかを国際社会から疑われている。政治をこんなにしてしまったのはもとをただせば選挙権を持つ民衆なのですから、民主主義の欠陥を嘆く気持ちはわかります。
しかし、では、人権保障や民主主義がない世の中とは一体どんなものなのか。
極貧のジャン・ヴァルジャンが、飢えて、パンを一切れ盗んだ罪で19年も奴隷状態だったのは1815年という設定です。そんなに昔のことではありません。そして、男の最低を象徴するのがジャン・ヴァルジャンなら、女の最低はファンテーヌというのが19世紀フランスの文豪、ヴィクトル・ユゴーの創作意図でしょう。二人とも、貧しさと社会の状況に追いやられただけで、もとは誰とも同じ、ごく普通の人です。
人権保障がないとはこういうこと。生き地獄は、本当にあった。『Do You Hear The People Sing?( 邦題:民衆の歌)』で人々が「二度と奴隷になんてなるか!」と怒りを直接、高らかに歌っているのはスカッとしました。
革命家の生き様やバリケードの様子も、生々しく描かれていました。歌詞の中に「Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? (拙訳:ある者は倒れ、ある者は生き延びるだろう。立ち上がって賭けてみないか?)」とありますが、そう、死者が出ることは前提なんですね……。そしてふたを開ければ、革命は失敗。バリケードの参加者たちは、撃たれ、刺され、死んでいった……そういう戦いなのです。「今日の人権は、数えきれない犠牲の上にようやく手に入れたものだ」とよく言いますけど、それが映像になると、ぐっとリアリティが増して胸に突き刺さります。
民主主義がなければ、王政打倒のために、殺されること覚悟で革命を起こさなければ明日がない。
本作がそういう時代を写実的に描いたのを観て、私たちはいわば、平和ぼけしているのかなぁと感じました。人権保障も、民主主義も、あって当然ではないんですね。世の中にちょっとうまくいかないことがあるからといって、呪いの言葉を吐き捨てられるような代物ではない。誰かに命じられたから大事にするものではなくて、心から尊いと思える、崇高なもの。自由と民主主義のため命がけで戦った人々には、時を越えて私たちに響いてくる意志がありました。
もっとも、『レ・ミゼラブル』の時代設定はフランス革命(1789年)より後なので、すでにかの「人権宣言」は存在していたわけです(原作小説はその時代に生きていたユゴーがリアルタイムに書いた作品なので、いわばリアルボイスである)。ただ人権思想はまだ芽が出たばかりで、あまり現実化はしていない、そんな社会状況。「人権宣言の紙切れさえあればオールオーケーで、人権保障がなかったのは過去のこと」というわけではないところは注意に値するな、と気づかされます。
原作小説よりも「ソフト」なシーンの数々
そんな出だし最悪のストーリーですが、これでも原作小説に比べれば過酷さは影を潜め、受け入れやすくなっていると感じました。原作との小さな相違点は挙げていったらきりがないので、私の心に留まったところだけ書いておきます。
いちばん大きいのは、ファンティーヌの最期でしょうか。原作では、病床に押し入ったジャヴェールが「マドレーヌ市長」の正体を暴露し、ファンティーヌはコゼットが大切に守り育てられるだろうという希望を打ち砕かれたショックで死んでいくという、あんまりなシーンなのです。映画版のファンティーヌは、ジャン・ヴァルジャンにコゼットを託して、幾分安らかな最期を迎えています。
それからエポニーヌ。このミュージカル映画版では最後までいい子として描かれていましたよね。ところが原作では怖い怖い! 原作のエポニーヌは、マリウスがバリケードに加わるよう一策を講じます。そして、戦闘でマリウスが死ねば永遠にコゼットとは結ばれずにすむという、狂気の喜びの中で息絶えていくのです……。ただこのエポニーヌ、読者の感情としてはあまりにかわいそうなんですよね。ろくでなしのテナルディエ夫妻のもとに生まれたがために、良い生活へ浮上できる見込みはなし。将来に何の希望もない中、唯一見られた夢が、同じく貧乏だけれど高潔な青年・マリウスだったわけですよ。そりゃあエポニーヌは小さい頃はちょっと嫌な子だったかもしれないけど、せっかく生まれてきたんだもの、少しくらい夢見たっていいじゃないですか! この映画は、そこまで哀れな子が陰謀を企てたとは「思いたくない」という、見る側の感情に重きを置いたのかもしれません。ほか、原作ではエポニーヌにはアゼルマという妹がおり、元気な浮浪児ガヴローシュは実は弟なのですが、この設定も本ミュージカル映画版では省略されています。ストーリー展開には直接からんでこないので、ややこしくならないよう言及を避けたのでしょう。
また、ジャン・ヴァルジャンのマリウスに対する視線は、原作よりうんとあたたかく描かれています。「Bring Him Home(邦題:彼を帰して)」の1曲を割いてまで、マリウスを善良で未来ある若者として見込んでいる。原作に出てくる、コゼットの心を奪った若者への憎しみはほんの一言にとどめられていました。
そしてマリウス。原作では、ジャン・ヴァルジャンから徒刑囚で逃亡中の身だと告白されると、彼をあからさまに遠ざけていきます。その点、本ミュージカル映画版では、マリウスの意図はコゼットが傷つかないために伏せておくということだったので、少なくとも原作ほど厳しくはありませんでした。もっとも、原作でのマリウスの冷たい態度は、19世紀当時の政教分離しきっていない刑法観に端を発しています。映画の制作者には、話の複雑化を避けたいという事情もあったのかなと思います。
以上のように、原作で精神的に負担の大きいシーンが、このミュージカル映画版ではだいぶ「ソフト」に変わっていました。私は歓迎です。なぜかというと、あまりにつらい内容だと観る気が失せてしまうから。それに、映画化の際には何もかもを原作通りにすればいいというものではありません。映画という表現方法だと、情報を詰めすぎれば作品として成り立たなくなってしまうからです。ラストシーンまでに何回も泣くエンタメ作品に仕上げてくれて、私はうれしかったですね。
目に優しい作風にしたのに、原作の良さを損なっておらず、不足がないところが本当に感涙でした。制作者の原作に対する愛情をいたるところに感じます。
時代を生きた、等身大の人々
ラストまでにここまで泣いた映画もめずらしい。私の中で大ヒットだった本作ですが、中でも個人的に好きなのは、革命家のリーダー・アンジョルラスの『The Final Battle』でした(ちなみにですが、このシーンは原作と言葉の表現等は違っている)。自分が倒れようとも、後に自分たちの思いを継いで、自由のため戦う者が現れるから――その生き様に心打たれてもう涙しかない!
しかし本作、どんなに劇的であれ、どう見ても英雄伝ではないんですよね。そこにいるのは、あくまでその時代を生き切った等身大の人物たちで。それを思うと、いやはやなんというか、人間賛歌がいつまでも耳に残る感じがします。
結びに―世にも貴重な、完璧な一本
今日『レ・ミゼラブル』と言ったとき、思い浮かべる作品は人によってまちまちでしょう。このミュージカル映画か、他の映画版か、それともヴィクトル・ユゴーの原作小説か、あるいは舞台や歌か。私のレミゼ鑑賞歴は、資料や他の映画等で触れたあと、ユゴーの原作に挑み、そのあと今回のミュージカル映画という順番です。どれであれ『レ・ミゼラブル』なら話は同じ……まぁそう言えなくもないですが、全部が全部、本作ほどのぼろ泣き作品ではありません。
私が「完璧」だと考えている映画は何本もないのですが、ミュージカル映画版『レ・ミゼラブル』はその貴重な一つです。『レ・ミゼラブル』としての完成度は群を抜いているし、映画としても傑出していると思います。映画の上映時間は限られていますが、そこに人の生を凝縮し、人の思いを増幅させ、生き生きと歌い上げたのはまさに映画の鏡。観て本当によかった。いいものを見させてもらって私は幸せです。
奴隷的苦役からの解放、人間らしい生活、自由への渇望。それらは時空を越えて決して絶えることのない人類の願いです。『レ・ミゼラブル』は、人々の声が聞こえてくる、情熱的でパワフルな作品でした。
関連記事・リンク
『グレイテスト・ショーマン』あらすじと感想―現代に響く人間賛歌 – ジャン・ヴァルジャンを好演したヒュー・ジャックマンが主演を務めたミュージカル映画の名作です。舞台は19世紀のアメリカ、差別に苦しんでいた人々のサクセスストーリー。歌やダンスの華やかさはもちろん、人間の尊厳に胸熱くなる作品です。
スターウォーズをキャラクターから読み解く – たっぷり語る前に、はじめての人向けガイドをつけておきました。食わず嫌いしている方も、これを聞いたらもうじっとしていられないはず――SF映画・スターウォーズは、悲劇の叙事詩である。腐敗した民主主義から独裁者が現れ、民衆自ら権力を手渡して破滅するのである。
『オペラ座の怪人』あらすじと感想―現代人にとって最も身近な「オペラ」 – ミュージカル映画の大作です。有名なパイプオルガンの曲はこのミュージカル版のもので、作曲は『ドレミのうた』などで世界中に知られているアンドリュー・ロイド・ウェバー。映画版キャストの歌唱も魅力的。
映画『きっと、うまくいく』あらすじや感想など―成功はあとでついてくる – 要所で歌やダンスがはさまるインド映画。ミュージカルが好きな人にぜひおすすめしたい映画です。経済成長著しいインドの学歴競争や若者の自殺など、シリアスなテーマをコメディで描いています。
映画『ボヘミアン・ラプソディ』あらすじと感想―クイーンの新たなロック伝説! – 伝説のロックバンド・Queenの伝記映画。ボーカルのフレディ・マーキュリーを主人公に、伝説が彼らの音楽とともにつむがれます。フレディのマイノリティとしての悩みなどもしっかり描かれていて興味深いです。貴重なライブ音源も必聴!
ララランドあらすじと感想―映画の都の音楽映画 – ハリウッドの音楽映画ですが、中心となる音楽ジャンルは渋くもジャズ。沁みるストーリーや細やかな心情描写、映画産業の歴史を見せてくれる美術など見どころもりだくさんな作品です。
『レ・ミゼラブル』はどれから見る?―おすすめ情報
本ミュージカル映画版は、私が知る全映画で5本の指に入る鉄板です。難解な作品ではないし、暗い作風でもありません。予備知識や気合いは特にいらないです。(ただ終わるまでに何度も泣くことになるので、それは計算に入れてから見始めたほうがいいとは思います。)
あと、『レ・ミゼラブル』に興味はあるけれど敷居が高くてなかなか手を出せない人は、太鼓判を押しますけどこのミュージカル映画から入るのが絶対おすすめ。原作に忠実で、しかも面白く仕上がっています。
ヴィクトル・ユゴーの原作小説『レ・ミゼラブル』
長い。長すぎる。けれど映画でストーリーの大筋を頭に入れてしまえば、けっこうサクサク読み進められると思います。一応、原作から大筋に関係ない部分を取り除いた『省略版』上巻・下巻というのが出ているのですが、興味があってもっと詳しく知りたい方は、この映画から原作へジャンプ・アップするのが私のおすすめです。ミュージカル映画版では省いてある登場人物や人間関係、細かい相違点なんかを発見しつつ……第4部には、おそらく永遠に映像化できないものすごい場面があるので、怖いもの見たさでどうぞお楽しみに。
フィクションというだけではなく、作者の主張やレポートのような性質もある「書物」なので、私のような文学青年から遠いタイプの人間にはむしろうれしい作品です。