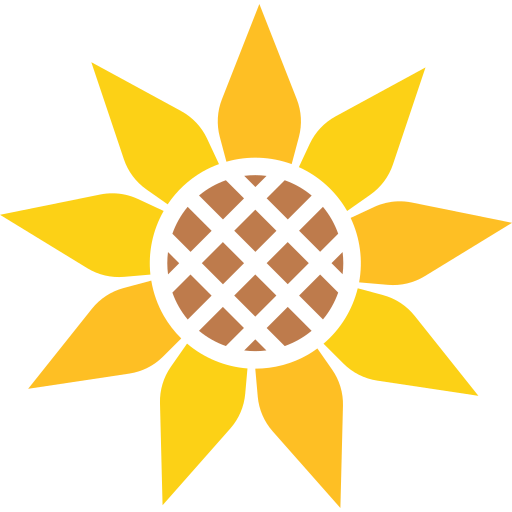『オペラ座の怪人』(原題:The Phantom of the Opera ジョエル・シュマッカー監督)は、同名小説を原作としたアンドリュー・ロイド・ウェバーによるミュージカルを2004年に映画化した作品です。
実は同作、これまでにミュージカル化は3回、映画化はなんと9回に及んでおり(2019年現在)、しかもそれぞれでストーリーやキャラクター設定まで異なっているという、作品事情からして怪奇なタイトルなのです。そのなかで、世の人が『オペラ座の怪人』と聞いて思い浮かべるのと合致する作品は、1986年初演、日本では劇団四季によって上演されているこのミュージカル版でまちがいありません。フィギュアスケートの定番楽曲となっているパイプオルガンのあの曲も、本ミュージカル版の一曲です。今回はミュージカル映画版『オペラ座の怪人』のあらすじをまとめ、音楽的な部分や過去作との比較なども含めた感想をつづりました。(以下、結末までのネタバレを含みます。)
目次
オペラ座の怪人 あらすじ
1919年、フランス、パリ。オペラ座で開かれた公開オークションでは、年老いた男性が猿のオルゴールを競り落とし、大事そうに抱えていった。彼にとって特別な思い入れのある品だったのである。
時をさかのぼること50年。1870年のオペラ座は、新作『ハンニバル』の初演を間近に控えていた。しかしここ3年、オペラ座では原因不明の事故が多発。「オペラ座の怪人」のしわざだとうわさされていた。姿を見せぬ「ゴースト」に要求通り5番ボックス席を空け、毎月2万フランの「給料」を払い続けてきた支配人は、神経をすり減らしてとうとう引退。中古金属業の成金であるフィルマンとアンドレが新支配人、若きラウル・シャニュイ子爵が新たなパトロンとしてやってきた。オペラ座のプリマドンナであるカルロッタが彼らに歌声を披露すると、何の前触れもなく天井から大道具が落ちてきて彼女は下敷きに。気位高くわがまま千万なカルロッタはかんかんに怒り、もう出演してやらないとわめき散らして出て行ってしまう。みなが困っていると、オペラ座のバレエ教師・監督であるマダム・ジリーは、代役としてコーラスの一人にすぎないクリスティーヌを推薦。驚くほどの歌唱をみせたクリスティーヌは代役に決まり、『ハンニバル』の初演は大成功を収める。彼女のもとには、黒いリボンが結ばれた赤いバラが届いた。
その夜、マダム・ジリーの娘でバレリーナのメグは、クリスティーヌに、一体どんな先生に習っているのかと尋ねる。クリスティーヌは親友に、不思議な秘密を打ち明けた。顔は見たことはないけれど声だけで語りかけてくる「音楽の天使」からレッスンを受けているというのだ。クリスティーヌの父はスウェーデンの名バイオリニストだったが、彼女が7歳の時、死の床で「天国に行ったら音楽の天使を送ってあげるよ」と最期の約束を残して他界した。両親を亡くしたクリスティーヌはオペラ座の寄宿生となったが、夜、あまりのさびしさに祈っていると、謎の声が語りかけてきたという。それからというもの、クリスティーヌはその声が天国の父が遣わしてくれた「音楽の天使」だと信じ、ひそかに歌を習い続けてきたのだ。
一方初演を鑑賞したラウルは、クリスティーヌが幼き日の恋人だと気付く。再会を果たしたラウルはクリスティーヌをディナーに誘うが、喜びもつかの間だった。クリスティーヌは何者かによって部屋に閉じ込められ、謎の声により、夢見心地で鏡の裏へ誘い込まれてしまう。
鏡の裏は、オペラ座の地下深くへ続いていた。クリスティーヌが仮面をかぶった謎の男に手を引かれ、途中からは馬で進み、水場を小舟で渡ると、その先には無数のろうそくが灯る神秘的な小部屋があった。仮面の男・ファントムは、そこに隠れ住み作曲に没頭する天才音楽家だ。彼こそが「オペラ座の怪人」の正体である。ファントムはクリスティーヌの秘めたる才能と美声を見抜き、彼女こそが彼の音楽を完全なものにできると考え、「音楽の天使」のふりをしてその心に深く取り入ったのだ。
喝采を浴びたソプラノ歌手がその晩何者かに連れ去られ、世間はうわさに沸き立った。そんなホラーストーリーを興味本位で楽しむ道具係のブケーやバレリーナたちを、マダム・ジリーは口を慎まなければ後悔するとたしなめる。長年オペラ座に在籍するマダム・ジリーや、裏方として舞台裏を駆けまわるブケーは、怪事件について何かを知っているようだ。
翌朝クリスティーヌは地下室で目を覚ます。ファントムは作曲の没頭していた。ずっと姿を現してほしいと願っていた、そしてかの「オペラ座の怪人」の正体であった彼の素顔に興味をそそられたクリスティーヌがそっとその仮面をはずしてみると、ファントムは激高する。仮面に隠された顔は、醜くつぶれていたのだ。ファントムはそのせいで生まれてこのかた誰からもあわれみを受けたことがなく、ひそかに美に、そしてクリスティーヌにあこがれているという。
翌日、関係者のもとには次々とおかしな手紙が届いた。支配人のフィルマンとアンドレにはクリスティーヌへの賛辞と「給料」の催促、ラウルにはクリスティーヌは「音楽の天使」の庇護下にあるので会おうとすれば災いが起こるとの警告、カルロッタには歌手生命は終わったとの侮辱。そんな折クリスティーヌは無事戻ってくるが、マダム・ジリーのもとにはカルロッタを降ろしてクリスティーヌを主演させなければ災いが起こるとの脅迫状が届いていた。「ゴースト」からの要求を煙たがるフィルマンとアンドレは、カルロッタを必死でおだててご機嫌をとり、新作『イル・ムート』の主演に、クリスティーヌを台詞のない小姓役に決める。
公演中の劇場内。突然「要求通りに5番ボックス席が空いていない」と謎の声が響き渡る。ファントムは手始めに、のど用スプレーに細工をほどこしてカルロッタにだみ声を出させ、大恥をかかせた。舞台は混乱状態に。支配人は準備もままならないバレエでその場をとりつくろうが、ファントムは道具係のブケーをロープで縛り首にして、公演中の舞台へ放つ。一斉に悲鳴が上がり、公演は惨劇に変わった。
その夜、クリスティーヌは「オペラ座の怪人」に会ったことをラウルに打ち明ける。ラウルはにわかに信じず、きっと夢を見ていたのだと言い、クリスティーヌを孤独と不安から守ると約束する。二人が愛を誓い合うのを陰から聞いていたファントムは、それぞれに対して嫉妬の炎を燃やし、復讐を誓うのだった。
『イル・ムート』の惨劇から3か月。その間「怪人」による事件はなく、平穏が戻ったオペラ座では仮面舞踏会が開かれた。みなが仮面をつけているため誰が誰だか分からない舞踏会にまぎれて、ファントムが現れる。新作オペラ『ドン・ファン』の楽譜を書き上げたので上演するようにと要求し、クリスティーヌに師のもとへ戻って来いと近づくが、胸に光るクリスタルガラスの婚約指輪に気づくと激高。オペラ座の内部を知り尽くしたファントムは、舞台の仕掛けから地下へ逃走した。捕えようとあとを追ったラウルは、マダム・ジリーに止められる。ラウルが問い詰めると、マダム・ジリーは彼女だけが知る「オペラ座の怪人」の秘密を語り出した。
少女時代の彼女は、バレリーナを目指すオペラ座の寄宿生だった。ある時、パリに東から旅芸人一座がやってくる。彼女が友人らと見世物小屋に入ると、そこでは顔が半分くずれた少年が檻に入れられ、「悪魔の落とし子」との触れ込みで見世物にされていた。見物人たちは彼を笑いものにしたが、マダム・ジリーだけは彼をあわれに思う。その時、少年は彼を捕らえている団員をロープで絞殺。殺人事件だとあたりが騒然とする中、マダム・ジリーは彼の手を引き脱走を助けた。以来、彼はオペラ座の地下に住み着き、音楽を友にひとり非凡な才能を伸ばしたのだという。
翌朝、クリスティーヌはひとり、馬車で家族の墓地へ向かう。ファントムが御者になりかわっていることには気づいていなかった。墓前で悲しみを語るクリスティーヌ。父が「天国から音楽の天使を送るよ」と言い残したのは幼かった彼女を怖がらせないためだと、頭では理解できる歳になった。父は逝ってしまい、再び戻ってはこないということも。しかしオペラ座の寄宿生となってからの年月、涙をこらえなかった時はなく、いまだ父に別れを告げることができない。心は過去の悲しみにとらわれたままなのだ。その時、墓地に声が響き渡る。物陰に姿を隠したファントムは、自分こそ父の魂だと語ってクリスティーヌを引き寄せようとするが、間一髪のところでラウルが到着。激闘の末勝利したラウルはファントムを殺そうとするが、クリスティーヌは情けを懇願。敗北したまま墓地に残されたファントムは、さらなる怒りと屈折を抱いてしまう。
ラウルはファントムを罠にかけようと策を講じる。ファントムが作曲した『ドン・ファン』にクリスティーヌが出演すれば彼は必ず現れるので、オペラ座を警官で固めておくという。自分や周囲の命が危険にさらされているものの、音楽を教えてくれた人を裏切るわけにはいかないと苦悩するクリスティーヌ。一方ファントムも、これが勝負だと地下で計画を練っていた。
『ドン・ファン』はついに開演。やがてクリスティーヌの出番になると、ファントムはドン・ファン役のテノール歌手・ピアンジを襲い、自らが役となって舞台に立つ。公演は順調に進むが、ラウルやマダム・ジリー、そしてクリスティーヌら一部の関係者はどこかに異変を感じ始める。『ドン・ファン』の情熱的な恋歌が最高潮に達したところで、ファントムは「望むのはそれだけだ」とクリスティーヌへ愛を告白。クリスティーヌが相手役の仮面を外すと、会場からは悲鳴が上がった。動き出す警官隊。ファントムは劇場の豪華なシャンデリアを客席に落下させ、その隙に舞台の仕掛けからクリスティーヌを地下へと連れ去る。大混乱のオペラ座は悲鳴に、そして炎に包まれた。
地下の隠れ家へ連れ去られたクリスティーヌは、ファントムの孤独と悲しみを理解し、その顔を恐れはしないと告げる。そこへ数々の罠をかいくぐったラウルが到着。しかし一瞬ふり返った隙にロープで捕まってしまう。ファントムは、自分に愛を誓えばラウルを生きて帰すが、そうでないなら殺すとクリスティーヌに選択を迫った。寄宿生となって以来、夢と現実の区別がつかぬほど慕い続け、正体を知ってからは深く同情してきたファントムが、苦しみを与えてきた――クリスティーヌは彼が「音楽の天使」でも父の魂でもないという現実に目覚め、初めて怒りをぶつける。その上で、彼の暗い人生をよく理解するクリスティーヌは、「あなたは孤独ではない」と、彼を暗闇へ追いやった顔にキスをした。生まれて初めて人間らしい扱い、人間に対するあわれみを受けたファントムは感涙にむせぶ。迫りくる警察の捜査。こみ上げる感情を通して、残酷な行いを重ねてきた自分はクリスティーヌと生きるにふさわしくないと悟ったファントムは、他言を禁じた上で二人を地上へ帰すと決めた。
立ち去り際、クリスティーヌは婚約指輪を外してファントムにプレゼントする。クリスティーヌがラウルと愛を誓いながら小舟で去るのを見届けたファントムは、「これで幕は下りた」と隠れ家の鏡をすべて割り、裏の隠し通路から地下道へ消えていった。警察とオペラ座関係者が到着するころには隠れ家はもぬけの殻となっていて、事件の手がかりといえば、猿のオルゴールのそばに残された「怪人」の仮面のみだった。
時は過ぎ、1919年。クリスティーヌはラウルに愛され年月を共にし、2年前に他界していた。年老いたラウルはクリスティーヌの墓に猿のオルゴールを供え、悲しみに震えるが、帰り際にふと、同じ墓前の赤いバラに気がつく。バラの花には黒いリボンが結ばれ、クリスタルガラスの指輪がはめられていた。オペラ座の怪事件から50年。ファントムはパリのどこかで生き続け、ひたすらクリスティーヌを想っていたのである。
感想―夢か現か、劇中劇のマエストロ
私にとって『オペラ座の怪人』という作品に触れるのは、中学での選択音楽クラスが最初でした。その後サラ・ブライトマン(ソプラノとポップスの歌手で、本作オリジナルミュージカル初演のクリスティーヌ役)のアルバムCDで、劇中歌を4曲聞いたことがあります。そして今回知人に「『オペラ座の怪人』は?」と言われ、そういえば結末まで見届けたことはなかったなと、本ミュージカル映画版に手をつけました。
全体としての感想は、「現代」に合った絶妙な作品だということ。ここでは、音楽、ストーリーやキャラクター、美術や演出それぞれについての感想と、私の個人的な見方などをまじえた思いをたっぷりつづりたいと思います。
メインキャストの輝く「歌唱」
オペラが題材の本作では、ストーリーより先に歌唱について述べるのが似合うと思います。
メインキャスト3人の歌唱はそれぞれ輝いていました。ファントムの秘めた激情をしぼり出すようなロックの歌唱。安定感と軽快さ兼ね備えたラウルの歌唱。私はとりわけ、やさしくて嫌味のないクリスティーヌの歌唱にとても好感を持ちました。
音楽には、楽しみ方にもパレットのように様々な色があるんですよね。その点本作は、ストーリーや歌詞というより「歌唱」自体に耳を傾けたいと思える、貴重な機会をくれる作品です。
貴重なサウンドトラックであの歌唱をもう一度!
音楽映画を鑑賞すると、普通の映画に増してサウンドトラックがほしくなるものです。効果音やセリフなしに、音楽だけでも堪能してみたくなるんですよね。私は本作が音楽映画として気に入ったので、サウンドトラックを探してみました。ところが……ない。ネットで検索しても、出てくるのはオリジナルミュージカルのサントラばかり。しかもほとんどが中古。いや、私はこの映画版キャストの歌唱で聴きたいんだよ! 海外では映画版のサントラが一応出ているらしいと突き止めたので期待はふくらんだのですが、輸入盤はアマゾンですら見つからない。ダメだ……。映画版の歌唱は映画で聴くしかないと、私はすっかりあきらめていました。
それがついに見つかった! AppleのiTunesストアで映画版のサウンドトラックが売られているのを見つけた時は、感動が胸にこみ上げてきてすぐに飛びつきました。私が調べた限り、国内で映画版のサントラが手に入るのはiTunesストアだけ。貴重です。
歌詞については次のストーリーのところで述べるとして、「歌唱」に耳をすませると、あらためてキャストそれぞれのハマリぶりにハッとさせられました。『Angel of Music』~『The Mirror (Angel of Music)』~『The Phantom of the Opera』の流れなど、純朴で「音楽の天使」にあこがれるクリスティーヌと荒々しくて怪しげなファントム、対照的な声と歌唱のかけ合いが際立っています。
メインキャスト3人それぞれ、歌唱が表情豊かですね。声色にいろいろな表情があるのはもちろん、ここぞというところでアタックを強めにしてアクセントをつけたり、はたまたセリフをささやくような箇所を入れていたり、こちらの心にグッとせまるところがあります。こういうところは「音楽」というより「演技」寄りで、ミュージカルらしい、映画らしいと思います。
あと聴いていて愉快になってくるのが、我らがプリマドンナ・カルロッタの『Prima Donna』。歌唱のベースはクラシックでありつつ、後述のぶっとんだ性格も表現されている。すばらしい歌唱力です。
クリスティーヌとカルロッタの曲には、クラシックのソプラノの域の高音が出てきます。ソプラノの声域といったら、たとえば私みたいに声楽を学んでいないごく普通の人が無理やりしぼり出したらノドをつぶしてしまう……ではなく、そもそもがんばったところで出っこないのでかえって安心というほどの高みなんですよ。カラオケが好きな人は、サントラを聴きながら「これを自分が歌ったら」と頭でイメージしてみると、そのすごさを実感できると思います。『オペラ座の怪人』という作品には、ストーリーの設定上、「声を楽器として使う」「声を聞かせる」ことを主眼とするクラシック音楽の世界がまざってくるんですよね。
私のプレイリストをいちばん下までスクロールしても、ソプラノの高音が出てくるのはこのサントラの曲だけです。ジャンルはクラシック音楽ではないにもかかわらず、ですよ。現代人のプレイリストに入っても、映画のサウンドトラックとしても、他とは違う異彩を放っている本作。『オペラ座の怪人』という作品の現代社会における絶妙な立ち位置をよく物語っていると思います。
ストーリーとキャラクター
『オペラ座の怪人』のストーリーは、テーマ性があるという方向ではありません。つまり、深く考えさせられたとか、社会問題に対する作者の主張へ共感したとか、そういう作風ではないんですね。ただ少人数のキャラクターがそれぞれよく立っているので、「舞台」には非常に適した構造のストーリーです。
私はこれまでこのブログで何本もの映画を取り上げてきましたが、このように解釈や想像の余地が広いストーリーだと、あらすじには自分の色がにじみ出ていると感じます。きっと書き手の個性によって、本作のあらすじは十人十色になるのでしょう。
さりげなくキラッと光った作詞
ストーリーなど言語的な部分では、クリスティーヌのソロ曲『Wishing You Were Somehow Here Again』にキラリと光るものを感じました。人の心深くにただようつかみどころのない心理を直接的に言語化した歌詞は、ストーリー中盤の何気ない一曲のようでいて、作詞者の細やかな観察眼を物語っていると思います。
喪失によってそれまでの幸せな世界が崩壊する経験は、そうかんたんに過去とはなってくれないんですよね。両親を失った時、クリスティーヌはまだ7歳。マダム・ジリーはよく目をかけていたようだし、寄宿生になったのだから生活には困らなかったはずですが、そのことが彼女の悲しみを消してくれるわけではありません。大事な人に、代わりはいないのだから。「それはもうないのだ」と理解する理性と、冷たい現実を受け入れられない心に生じる段差を、この曲はよく描いていたと思います。
そして私が繰り返し称賛したいのは、クリスティーヌ役のイメージにぴったりな歌唱です。もしも私が本作の監督だったら、クリスティーヌ役オーディションでこの声質・歌唱を探し出せた瞬間、空に向かって腕を突き上げたと思いますね。
「怪人」の変遷は時代の変遷を映す鏡
過去9回の映画化でストーリーやキャラクター設定がすべて異なる同タイトル、とりわけ「怪人」は毎回全然違うんです。私は選択音楽の授業でいくつかを見比べたりしたんですけど、今回その自分史に最新の作品を加えると、「怪人」の変遷は時代の変遷だなぁとしみじみしました。
昔の作品では、「怪人」はとにかく偏執的で、人間離れした怪物のように描かれているんですよ。ジャンルとしてホラーなんですよね。中学の音楽室では、私も、友達も、音楽の先生まで「怪人ストーカーだ!」なんて指さしていたくらい。
ただ現代の人は、理由もなく怪物じみた人間が出てきた時点で「安っぽい」と感じてしまいますよね。だからでしょうが、新しい時代になるほど、映画化の際には「彼」が「怪人」になってしまった理由付けがなされる傾向になっていきました。「天才音楽家ゆえの狂気」という側面も色を増してきている感じです。
そして2004年公開の本ミュージカル映画版では、「怪人」こそ最も観客の心に近いキャラクターとして描かれています。ホラーテイストは影を潜め、夜と昼、野性味と正統派、そして醜と美を対照にした三角関係のロマンスが前面に。
クリスティーヌに心を救われた次の瞬間から始まる、50年の歳月が重いです。せっかく素顔の自分でいられるようになったのに、殺人犯として追われるファントムは表舞台には決して出られない。「怪人」から人間になれて新しい人生が開けた途端、彼が進む先は暗い地下道以外にない。「自分の音楽に翼を与えられるのは彼女だけ」とつぶやいていたところをみると、クリスティーヌが去ったことで音楽はやめてしまったのでしょうか。せっかく天才なのに、もうその才能を披露することはない。50年もの間彼がパリのどこでどうやって生きてきたのかは誰も知らない、観客も含めて……。あまりに長い歳月の一日一日を想像すると、胸に刺さります。
結末のお墓を見るにクリスティーヌとラウルは幸せに暮らしたようですが(妻・母として愛され、しかもなにげに子爵から伯爵へ爵位が上がっているのでは?)、その50年間、ファントムのほうは何を想っていたのでしょうか。実はこれ、映画の冒頭でクリスティーヌが代役として歌う『ハンニバル』の劇中歌『Think of Me』がファントムの行く末を暗示しているんですよね。スタッフクレジットが流れ去ってから冒頭に戻った時の、あのすさまじい衝撃たるや! 一度通して見ただけの人やDVDが手元にある人は、ぜひ結末から冒頭へループで見てほしいです。私は打ちのめされました。ファントムにとって「音楽の天使」だったクリスティーヌがそれを歌ったというところがまた劇的で、悲しみがつららのように刺さってきます。
先に述べた通り、本作のストーリーにテーマ性はありません。私なんかだとつい、一人の人間を暗い運命へ引きずり込んだ人々や社会の在り方に注目したくなるんですけど、作中にこれといった意見などは盛り込まれていないんですよね。そしてだからこそ、そういった外部的なこと抜きで、ファントムという人の生だけにスポットライトが当たる。本作はそういう作風です。
50年におよぶ絶対的な虚無、そして孤独。救われたのに、救われたからこその苦しみに涙です。理屈ではない感動をくれるラストでした。
わがまま姫・カルロッタに爆笑!
と、ストーリーの本筋は孤独だった者同士の結ばれ得ぬ恋、悲しい愛の物語である本作ですが、メインを取り巻く面々はコミカル方向でも華やかですね。
とりわけ、周りが必死でちやほやしないとイタリア語でわめき散らしてどうにもならなくなるカルロッタには笑ってしまいました。なんじゃありゃ、女王様か!? いや、わがまま姫かな??
「あなたこそスターです」「みながあなたを待ち望んでいます」「外で長蛇の列をなすファンをお見捨てになるので?」「世界はプリマドンナにかしずきます」――ここまでおだてないと歌わんのかい! 気位が高いリード・ソプラノと聞けば、普通はシリアスな方向を思い浮かべるじゃないですか。他人がいくらうらやんでも望めないような高い歌唱技術と、それで手に入れた地位へのプライド。厳しくて恐ろしい絶対的トップが若き主人公の前に立ちはだかる……なんていう展開ならありそうですよね。それが本作のカルロッタは、度外れなわがままのために嫌われていて、一部ではむしろ馬鹿にされている、全身ショッキングピンクのぶっとんだキャラに。私はこれはこれでいいなと楽しめました。
というのも、わがまますぎてもはや奇抜なカルロッタ、ソプラノ歌手としての実力はピカイチであることは忘れてはならないんですよね。もったいぶった歌唱はファントムに「気取って舞台を行き来するだけ」と言われても仕方ない……というキャラクター性まで映画ではよく表現されていましたが――これも優れたキャスティングがなせるわざですね――それもカルロッタに確かな実力あってこそ。
声楽は非常に精密で、心構えを一歩まちがえればノイローゼになるような一面を持っています。ほんの一例ですが、A3、一般的にいう「ラ」の音は442Hz(クラシックの場合)だと決まっていて、これを声で出す時、声帯は1秒に442回振動します。これが1秒で443回になったら「ちょっと高いぞ」ということに。「より正確な音程で歌える歌手が……」などと音楽ライターは気軽に言うけれど、それはこんな信じがたい細かな差を指しているのです。
オペラ座の他の歌手たちにはそういうごくわずかな差がわかるわけだし、目が肥え耳の確かな観客だって見抜きます。高度な技能を身につけるには長年の努力と鍛錬を要するし、だからプリマドンナはみなの羨望の的に。決して派手なだけでスターになれる世界ではありません。
芸術の道の厳しさが下地にあるから作品全体からすっぽぬけたりせず、コミカルでありながら説得力を保持している。どピンクなカルロッタは、案外深い味を出していました。
劇中劇の美術の妙
舞台裏のセットや、天井から動かす道具の数々。歌手がせり上がって登場するための床のしかけ。舞台手前のオーケストラボックス。道具置き場のめくるめく鏡。
オペラを鑑賞するよりもオペラがわかる――『オペラ座の怪人』という作品には、そんな他に代えがたい魅力がありますね。
私の音楽の先生が本作を選択授業の題材に選んだ理由は、まさにここにあったわけです。その先生は「眠くなったら寝ていいよ~」なんて口にしている抜け感のある人で、実際普段の音楽では暗幕を引いてピアニストのビデオをかけたりすると机に突っ伏してゴロゴロするクラスメートがたくさんいたんですけど、多感な盛りだった私には次々映し出されるオペラ座の内部が面白くて、目を輝かせ耳をそばだてていました。だからとても印象に残っています。
本ミュージカル映画版もそれらをぬかりなく映してくれたのはうれしかったですね。しかもこれは物理的な制約がある舞台でなく映画なので、上演前にバレリーナたちがバタバタ準備している様子とか、衣装係や掃除係の仕事風景、道具類が雑々置かれた舞台裏、あとは舞台のそでから見た上演中の舞台なんかもたっぷり堪能できます。私としてはクリスティーヌが怪人とレッスンしている場面も入っているとうれしかったんですけど、絵として地味すぎてミュージカルには向かなかったのでしょうか。
過去9回の映画化で内容は毎回違うとはいえ、共通して使われているイメージはいくつもあり、それらはどれも劇場の内部構造にかかわる部分です。一つは、怪人が道具係のブケーを舞台上部で追いかけてロープで絞め殺し、上演中の舞台へ放つシーン(これはもろにホラー!)。あとは怪人が仮面舞踏会にまぎれて現れるシーン、舞台のしかけから逃走するシーンなんかもそう。ミステリアスな鏡や、なんといっても豪華なシャンデリアの落下は毎回目玉です。劇場を舞台に巻き起こるドラマが『オペラ座の怪人』独自の面白さだと思います。
どれが夢でどこからが現実なのか、夢見心地のクリスティーヌを軸とした物語。誰が誰なのか、近しい人にも判別できない仮面舞踏会。「どこから演技、どこから本当なの?」とハラハラする展開。もともと劇中劇が活きた作品をさらに美麗に幻惑的に表現した美術・演出に、私はとても満足です。
結びに―現代人が「オペラ」に触れる絶妙な立ち位置の作品
『オペラ座の怪人』の舞台である1870年から百数十年。本ミュージカル映画版は、現代人がアートに求めるものを絶妙な形で満たす、絶妙な作品だと思いました。
幸か不幸か、現代においてオペラは「超」がつくハイ・カルチャー(上位文化)に属しています。日常からは遠い、高級な文化。そう感じない人はいないでしょう。
私たちがオペラに触れる機会は、それこそ学校の選択授業で音楽をとったりでもしない限り、ないと言っても過言ではありません。私は選択音楽クラスで『アイーダ』を鑑賞したのを覚えていますが、それは授業だったので、先生がストーリーの舞台設定や登場人物の人間関係、それから使用される楽器にまで解説をつけてくれました。しかし一般社会へ出てしまえば、何百年も前の遠い国で作られたオペラを理解するには、設定や登場人物、ともすればストーリーの結末まで、自分で「予習」しておかなければなりません。映画館のようにふらっと入って楽しむ、というわけにはいかないのです。
そしてオペラを私たちの日常から遠ざける決定打は、あまりに高額なチケットです。オペラでは、チケット1枚が4~5万するのは少しもめずらしくありません。私の知人の知人は、「定年退職したらオペラのチケットを買って、全身着飾って出かけると決めている」と口にしているとか。オペラに行くのが「長年の夢」という立ち位置となっており、しかも作品自体というよりは「ゴージャスな気分にひたる」ことに重きがある様子がにじみ出ていて、それを聞いた私はなんともいえない気分になりました。
しかし、オペラの「本場」ではどうだったのか。『オペラ座の怪人』の舞台は、1870年のパリのオペラ座。当時の「劇場」を描いています。オペラにハイ・カルチャーとしての性質がなかったとは言いませんが、くだらないネタにどっと笑う観客などを見れば、だいぶ娯楽性がある様子をうかがえますよね。しかもオペラ座の名は「オペラ・ポピュレール(Opera Populaire)」、直訳するなら「大衆オペラ劇場」といったところ。芸術ではあるけれど娯楽性を多分に備えている、そういうオペラの在り方がみられます。
現代日本における「ハレの日のクラシック」「お高いクラシック」に問題意識や危機感を持ち、「もっと気軽に楽しんで」と訴えている人々はいます。この問題に単純単一な答えがあるとは思っていません。物事は大衆に広まりさえすればいいというほど単純ではないし、その背景は明治以降の世界情勢等もからんで複雑だからです。しかし、その考えには私も共感しています。人間の楽しみには色相環のように多様なカラーがあり、クラシック音楽もその一色に数えられるものであるべきだ。いろんな色の楽しみを自分の胸にそろえたほうが、人生は豊かになる。私はそう考えています。
さらにオペラの内容へ言及すると、「古典ばかりなのが問題だ」と現代日本が舞台の創作オペラをやっている音楽家はいます。しかし、お世辞にも盛んとはいえません。オペラから派生した「ミュージカル」の世界だったら、劇団四季『ライオンキング』のロングランなどが記憶に新しいですね。ただなお、ミュージカルは敷居が低いとまではいえないでしょう。
そこをいくと、『オペラ座の怪人』は現代人にとって、「娯楽」の範囲内にありながら「オペラ」という世界に触れられる絶妙な立ち位置にある作品だと思います。知識と資金が必要なハイ・カルチャーではなく、また数年に一度ブームになる「大人の教養」的な「勉強する」という感覚でもなく、純粋に楽しむ気持ちで鑑賞できるからです。敷居はきわめて低いです。レンタルビデオ屋なら『スターウォーズ』や『ドラえもん』と同じ立場で棚に入っているんですから。
そして「娯楽=エンタメ」としてはクオリティが非常に高いのも、『オペラ座の怪人』という作品ならではだと思います。人々に息抜きを提供するエンタメというジャンルでは、作品によってクオリティに月とスッポンの差があるのが常で、「スッポン」のほうになればもう目も当てられない……だけならましなほう。楽しい気持ちになるどころか、むしろ社会的に問題があり不愉快になるような「商品」も平然と流通しているのが実情です。このことは芸術の一分野・文学も同じなので、私にも厳粛になるほどよくわかります。そこをいくと『オペラ座の怪人』はオペラを題材とする以上、作品の完成度を求めるならキャストの歌唱力なしには制作することができません。芸術の厳しさが下地にあるから、成り行きとしてクオリティが上がり、満足度の高い作品になっていくのだと思います。ポップ一色な趣味もいいけれど、ハイレベルな作品を求める気持ち、優れた「歌唱」を聞きたいという望みは誰の胸にもどこかにあると思うんですよ。その気持ちを巧みに引っぱり出して、満たしてくれる。それが人気の秘密ではないでしょうか。
想像の余地がうんと大きいから何度見てもおもしろいし、「歌唱」自体もリピート再生したくなる本作。もしかしたらこれをきっかけに、今度はミュージカルを観劇したい、ソプラノ歌手が来るクラシックコンサートで生の歌唱を聞いてみたい、などと興味の幅が広がるかもしれません。
現代において絶妙な位置にあるミュージカル版『オペラ座の怪人』は、1986年の初演以来、日本でも劇団四季によって上演されるなど人々に広く親しまれる人気作となっています。この事実をふまえた上で、芸術――とくに音楽・舞踊・演劇などパフォーミングアートに属する分野、とりわけクラシック音楽――は、今後どのような方向に進んでいくべきだろうか、どんな試みが可能だろうか――。本作は、人類にとってもっとも重要な活動の一つであるアートの行くべき道について、自分なりに考える、よいきっかけになってくれると思います。
関連記事・リンク
著者・日夏梢プロフィール||X(旧Twitter)|Mastodon|YouTube|OFUSEではブログ更新のお知らせ等していますので、フォローよろしくお願いします。
映画『レ・ミゼラブル』あらすじ・レビュー・感想―人の願いは時空を越えて – 同じくパリを舞台とした、情熱的なミュージカル映画。私が完璧だと太鼓判を押す、数少ない一作です。こちらは『オペラ座の怪人』と反対に、原作者ヴィクトル・ユゴーの主義主張がぎっしり詰まったストーリー。フランス革命から日が浅い、人権という概念は芽を出したばかりでまだ根付いていない、そんな時代に生まれた人々を描いています。そしてクライマックスは、パリの地下(『レ・ミゼラブル』では下水道)が舞台となっているんですよ。パリの地下は、作家たちに「誰かが潜んでいる」とインスピレーションを与えてきたんですね。
『グレイテスト・ショーマン』あらすじと感想―現代に響く人間賛歌 – サーカスを舞台としたミュージカル映画の名作・ヒット作。ファントムが顔のことで闇に追い込まれたように、この作品では障害や肌の色など、見た目のせいで社会から嫌われ、排除されてきた人たちが主役となっています。必ずしも上流文化とはいえないヨーロッパのオペラ事情も垣間見ることができます。
映画『ボヘミアン・ラプソディ』あらすじと感想―クイーンの伝記は新たな伝説に – こちらはロックの音楽映画。ストーリーは伝説のロックバンド・クイーンのボーカル、フレディ・マーキュリーの伝記で、ロックの音楽と歌唱をたっぷり鑑賞できます。クイーンが代表曲としている『ボヘミアン・ラプソディ』ですが、これまたインスピレーション元はオペラだという点が興味深いです。フレディがオペラというものをどう見ていたのか作中で直接言及されており、この作品からもまた、現代人が求めるものとオペラの関係を考えさせられます。ストーリーは最初から最後までクイーンの歴代名曲とともに展開され、貴重なライブ音源も使用されています。
映画『ロケットマン』あらすじと感想―ロックと美と現実性のアレンジメント – ピアノロックの大スター、エルトン・ジョンの半生を描いたミュージカル映画です。エルトンはロックスターですが、音楽的に彼の出身はクラシック。イギリスの王立音楽院で奨学生としてピアノを学び、孤独な十代にロックへ傾倒していったという経歴の持ち主なのです。ジャンルによって別世界のように見える音楽の世界ですが、クローズアップしてみればクロスオーバーは頻繁に起こっている。そんな一面を見ることができます。
ララランドあらすじと感想―映画の都の音楽映画 – アカデミー賞6部門受賞した、ザ・ハリウッドのミュージカル映画です。私がおもしろいなと思ったのは、この『ラ・ラ・ランド』で歌われるのは、声量を出さず、即興のスキャットにスウィングの軽快なノリが良しとされるジャズ音楽だというところなんですよ。『オペラ座の怪人』はクラシックの歌唱がフィーチャーされ(本映画版のもとはミュージカルですが、どのみちミュージカルはオペラからの派生です)、上記『レ・ミゼラブル』はまさにミュージカルといった迫力の声量に朗々とした歌唱が響き、『ボヘミアン・ラプソディ』はロックの自由な精神とステージパフォーマンスで熱くなれる作品。そこをいくと、声量を出さないジャズを中心に据えた『ラ・ラ・ランド』は音楽映画としてユニークな立ち位置にあるし、「映画」の音響・録音設備が前提だからこそできた作品だと思います。美術にも強いこだわりがみられ、音楽映画の往年の名作『シェルブールの雨傘』へのオマージュもたくさんつまっています。音楽映画が好きなら観てよかったと思えるはず。
映画『きっと、うまくいく』あらすじや感想など―成功はあとでついてくる – こちらはインドの音楽映画……というより、インド映画(ボリウッド映画)というのは歌とダンスが組み込まれているものなんですよね。現地では、歌とダンスのシーンになると観客も立ち上がって歌ったり踊ったりしていっしょに楽しむんだとか。学歴競争や若者の自殺といった深刻な社会問題を笑いで乗り越える、コメディの傑作です。
年齢で追う尾田栄一郎さんの経歴と『ワンピース』の歴史 – 『オペラ座の怪人』に実は『Love Never Dies』という続編があったことはご存じでしょうか? 評判は散々で、ファンをかんかんに怒らせ、日本ではほとんど視聴不可能。なぜそのような作品が上演に至ったのか、「二次創作テイストと素人臭さ」の項からどうぞ。
純文学とエンタメ作品の定義と実情―一人ひとりが一作一作判断しよう – 「芸術」と「娯楽=エンタメ」の区分について、文学の実情を大事にふまえながら真剣に論じました。文学がたどってきた歴史や文脈と音楽のそれには差異があるとはいえ、根底にある私の問題意識、そして強い思いは同じです。
2019年4月12日公開。2020年11月5日、サウンドトラックを見つけて買ったのでその感想「貴重なサウンドトラックでその歌唱をもう一度!」を追記しました。