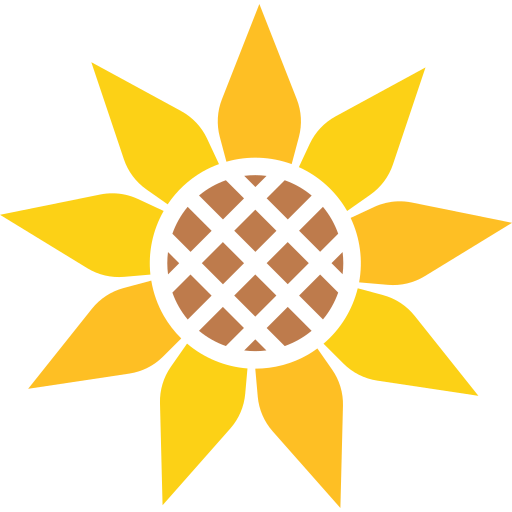「孤独死」は現代日本社会のテーマの一つである。将来に漠然とした不安を抱く人も多い。
だが、その取り上げられ方は無造作で、論点が整理されているとはいえないのが現状だ。世間ではイメージ先行のきらいがあり、メディアの報道では興味本位だったり、暗い不安感情をあおったりするものも少なくない。この問題意識から、筆者は、どういうケースが、どう問題なのかを確定させるべく、様々な事例にあたっていった。
それらを整理しながら見えてきたのは、第一に、孤独死は戦後日本社会の病の表れの一端だということだ。そこには、戦後幾久しくなっても未だ解決できていない課題が浮き彫りとなっている。日本人が意識や考え方を変えることが必要だ。そしてもう一つは、助かるはずの命があるということだった。
本稿では、孤独死と呼ばれ得る様々な事例を整理して、問題となるケースを見定め、論じていきたい。
目次
孤独死は問題なのか?
「孤独死」という言葉はよく聞かれるが、実はその定義はあいまいで、統一はされていない。そのため、一口にそう言っても、具体的な中身には幅がある。社会問題として扱うべき非常に深刻なケースもあれば、別段問題ではないようなケースもまざっているので、全部を一緒くたに扱うべきではないだろう。
問題ではないケース
まず、世間で「孤独死」と呼ばれる中には、臨終の際に医療者や家族に囲まれる「看取り」なしに一人で亡くなり、発見が後日になっただけのケースも含まれている。
こうしたケースは、以下で述べるような深刻な事例とは同列に扱うべきではない。なぜなら、もとより人がいつどこでどのように亡くなるかは、さほど選べるものではないからだ。たとえ自分が理想とする人生の終わりを思い描き、準備を整えていようとも、実際の臨終がそれ通りになるとは限らないのである。ほんの一例だが、外出先で突然倒れてそのまま他界するということは普通にあり得るだろう。その場合は、ベッドを取り囲まれて家族や知人に別れをする、といったことはなくなる。これは人の力でどうにかできることではないし、社会的にあってはならないことでもない。
人によっては、家族や知人に看取られて臨終を迎えたいと望んだり、他人が「看取り」なしに亡くなるのをかわいそうだと感じたりするだろう。ただ、それは個人的な感性や価値観にすぎないので、社会問題として取り扱うようなことではないのである。
社会問題というべきケースとは?
このように全く問題ではないケースが多くまざっている一方、社会問題としてとらえ、対処法を探っていかなければならない事例もれっきとして存在している。
近隣住人や不動産業界が頭をかかえている問題
問題の一つとして、まずは住まいに関する側面が挙げられる。高齢者等が一人で亡くなった後に放置され、遺体が腐乱臭を放つようになったことではじめて近隣住人が気づいた、というのである。発見の時点で親族など住居に入れる者が見つかればよいのだが、そうでないと近隣住人らが悪臭に苦しみ、健康被害が出ることもある。
また、不動産業界では、物件の事後処理が困難なことから、頭の痛い問題として持ち上がっている。こうしたケースは全国的に発生しており、もはやめずらしくないと言う関係者もいる。
本人の命と尊厳―助かったはずの人が亡くなっている現実
無論、亡くなった本人の命や尊厳に関する問題点もある。以下で述べていく中には、制度や医療があるにもかかわらず、それが使われないまま孤独死に至ってしまったケースが多く見受けられるのである。
ざっと指摘すると、認知症や精神疾患にはれっきとした医療がある。介護には様々なサービスや支援制度、経済的困窮には生活保護など社会保障制度が存在している。もしそれらが使われれば、彼らの命は助かったはずなのである。
孤立ゆえに人が生命を維持できなくなるという痛ましい結果は、日本社会に内在する要因から生まれている。本稿では、そうした社会問題として扱うべきケースについて、その背景を精査し、論じていこうと思う。
孤独死の様々な原因―一人暮らしの高齢者とは限らない
一般には、「孤独死」というと一人暮らしの高齢者が気づかれずに亡くなるイメージが強いと思われる。
確かにそういったケースはあるのだが、実際には、原因は様々である。亡くなった人が一人暮らしでないケースは多く、また必ずしも高齢者とは限らない。たいていの場合、家族との関係など、その人の抱えていた個人的な事情もからんでいる。日本の歴史的・社会的背景もある。社会的孤立から生命を維持できなくなるのは、こうした様々な困難の終着点だといえるだろう。
一人暮らしかつ閉じこもりがち
まずは、一人暮らしの高齢者に多いケースを解説しよう。高齢化社会の問題として、たびたび取り上げられている。
「一人暮らし」というのは、必ずしも独身だったことを指すのではない。配偶者が先立った、あるいは存命していても入院しているなどの理由で一人暮らしとなることはかなりの高確率で起こる。子がいたとしても、就職などの都合により、親元で暮らすのは難しいことが多い。
高齢者が家族と同居していたり、介護施設等で共同生活を送っていれば、体調等に異変があった際に周囲が気づいて適切な対応をとることができる(ただし、同居する家族が死に気づかないケースがいま各地で多発している。詳細は後述)。また、自宅で一人暮らしを送っている場合でも、
- 訪問看護が定期的に来る
- サークル活動や友人との交友がある
- デイサービス等に参加している
といった人との適切なつながりがあれば、やはり異変は発見される。
問題となるのは、一人暮らしかつ社会とのつながりが希薄な場合である。もともと高齢世代では、人柄が閉鎖的で、家に閉じこもりがちな人が多い。また、地域の古いコミュニティは、近隣同士での監視や詮索、陰口などが蔓延していることが少なくない。こうした場合、たとえ表面的には近所付き合いや地域活動が行われているとしても、メンバー個々は深く孤立している。互いに本音や困りごとを話せる相手ではないのである。実質的には「社会とのつながり」とはいえない。
社会との適切なつながりがなければ、体の衰えや、次に述べる認知機能の低下、生活への支障、あるいは突然倒れたなどの緊急事態が見過ごされる。その結果として生命を維持できない状況に陥り、命を落としてしまうのである。
認知症
超高齢化とともに世間で広く知られ、時に「最もなりたくない病気」などといわれる認知症は、孤独死の原因として代表的である。
認知症とは、老化や脳の病気などにより認知機能が低下することで、日常生活や対人関係に支障が出る状態の総称である。具体的には、物忘れ、理解力の低下、時間や場所が分からなくなる(見当識障害)などが中核で、周辺症状としては抑うつなども生じやすい。
国内の患者数は、2012年時点で462万人、65歳以上の約7人に1人とされているが(平成28年度版高齢社会白書、内閣府)、正確な数は分かっていない。なぜなら、認知症には明らかにそれらしい状態であるにもかかわらず、医療機関で診断・治療を受けていない「暗数」が多いとみられるからだ。
なぜ受診しないのかというと、第一には、本人に病識がないことが多いからというのが挙げられる。自分の認知機能が下がっているため、物忘れをした、理解力が低下している等を自分では正確に判断できないのである。また、症状がそこまで悪化しておらず、衰えや物忘れを自分でうすうす察知していたとしても、医療機関を受診したがらない人は多い。「自分が誰かも分からなくなってしまう」といったイメージにより、認知症と診断されるのを恐れるのが大きな原因である。
こちらも、元気なうちから社会との適切なつながりがあれば避けられるのだが、そうでないと症状が悪化するにつれてどうにもならない状況に陥っていく。認知症が進行すれば、生命を維持するのに十分な食事や身の回りのことが自分ではできなくなる。しかも、医療機関や高齢者福祉施設で相談するなど、自力で支援を求めることもできない。その結果として低栄養や不衛生などに陥り、命が危険にさらされるのである。
老老介護と認認介護
超高齢化を背景に、介護現場等で大きな問題となっているのが、「老老介護」と「認認介護」である。
老老介護と呼ばれているのは、介護をする側とされる側がどちらも65歳以上だという状況である。これには、
- 高齢カップルの片方がもう片方を介護している
- 80代の親の介護を65歳の子が担っている
- 高齢のきょうだいが同居している
といったケースが含まれる。
老老介護は、介護する側も老化していて負担が大きいため、うつや自殺、虐待などにつながるリスクが高いとしてこれまでも問題となってきた。身体的な疲労や抑うつなどから、家に閉じこもりがちになったり、動こうにも動けなくなくなったりしてしまうことが、上記と同じように生命を維持できない原因となる。
八方塞がりの認認介護
さらに、最近では「認認介護」にもスポットが当たるようになった。認知症患者の介護をしている高齢者が、こちらも認知症だ、というのである。
介護をする側の認知能力が低下していれば、生活の介助はおろそかにならざるを得ない。さらに症状が進行すれば、介護を放棄しがちになる。他人の世話をするどころか、自分の生活能力すら失われているからだ。例えば、記憶障害により朝食を食べたかどうかを忘れてしまったりするようになれば、二人とも十分な食事をとれずに低栄養を引き起こす。片方の容体が悪化したり、亡くなった時にも、救急車を呼ぶなどの適切な対応ができない。
家に閉じこもったまま認認介護が続けば、最終的には共倒れになる。火の消し忘れから火事になった、片方がもう片方に暴行したなど、刑事事件となって明るみに出るケースもある。中には、認認介護夫婦の妻が夫を殺害したが、自分がしたことや夫の死を認知できていなかった、というショッキングな事件も報告されている。
引きこもり
自宅や自室から出られない「引きこもり」は、その人個人の性格や弱さによるのではない。戦後日本社会が抱える深刻な病の表れである。国際的に高く評価された宮崎駿監督の代表作『千と千尋の神隠し』がそれを中心的テーマに据えているほどである。別途論じたので詳しくはそちらを参照してほしい。
関連記事:中年の引きこもりと仕事のジレンマ&今後のライフスタイル
引きこもりの人がしだいに中高年となりつつあるいま、親が他界した後にそのまま亡くなりかねないことは、新たな問題として知られつつある。
経済的困窮
高齢者のイメージが強い孤独死だが、実際には中年や、若ければ20代など、幅広い年代でみられている。
主要な原因の一つは、経済的な困窮である。雇用面での不遇、失業などから経済的に追い詰められると、生活が切り詰められ、おのずから行動範囲も狭くなる。ストレスや将来不安から精神疾患を患うことも、さらなる行動の足かせとなる。こうして困窮を一人で抱え込んだまま、自殺や死去に至ってしまうのである。
「同居孤独死」―家族が死に気づかないのはなぜ?
先に少し触れた通り、いわゆる「孤独死」で亡くなった人の中には、一人暮らしではなく、家族と同居していた人もいる。家の中で亡くなっていたのに、家族が気づかなかったのである。なかには、遺体が異臭を放つようになってはじめて家族が死を知った、というケースもある。これは例外的な話ではなく、全国各地で相次いでいる。
同じ家で暮らしていれば家族が息絶えているのに気づかないほうが難しそうなものだが、なぜそのような結果になってしまったのだろうか?
その原因は次の二つに大別される。
一つは、同居家族が認知症で理解力等が低下していたり、要介護の状態だったりすることである。こちらは前述した。
もう一つの原因は、家族関係が希薄だったり、もともと不和や機能不全を抱えていたことである。
たとえ関係自体は良好だったとしても、顔はあまり合わせない、ということはあり得るだろう。家族にもそれぞれの生活があるからだ。
そうではなく、家族関係に問題を抱えていたケースもある。不仲なので互いに会わないよう部屋を分けていた、といった場合だ。「厳しい」父親が「部屋には絶対入るな」と家族に言いつけていた、といったケースも報告されている。書面の上では同居していることになっていたとしても、実質的にはそうではないのである。
腐乱臭から親の死に気づいた後に、同居していた子が遺体を放置したとして逮捕される事件も各地で相次いでいる。NHKの「クローズアップ現代」の取材によれば、逮捕された子は取り調べに対し、親の死に気づいた際「どうしたらいいか分からなかった」「怖かった」などと話しているという。根の深い心理的要因といえよう。
このような「同居孤独死」は、その家族が抱える長年来の様々な要因が複雑にからみ合った末の結果なのである。
対策の大原則は「孤立の防止」
以上、人の命と尊厳にかかわる深刻なケースを見てきたが、この問題は、どのようにしてそのような事態に陥ったのかが明らかになれば、対策はおのずから見えてくるといえるだろう。孤独死の原因を見ていくと、生命維持不能に陥ったのは、いずれも社会からの孤立が発端だということが分かるのである。
そもそも、ヒトは、一匹オオカミのように生命維持を自己完結できる生き物ではない。栄養を得るまでのプロセスは複雑だ。食材の調達、調理といった、食べる直前の段階ですら、足腰の弱った高齢者には負担となる。たとえ若くても、失業や低賃金といった問題は独力では解決不能だ。医療機関とつながらなければ病気は悪化し、いずれは命を失うだろう。人間が自力でできることは限られているので、足りない分は外部から取り込んでいかなければならないのである。
老後対策のポイント
まず、老後の孤独死を避けるための対策では、本人が「元気なうちに」社会から孤立しない態勢を整えておくことがポイントとなる。足腰の自由がきかなくなったり、認知機能が落ちたりしてからでは、孤立を解消しようにも動くに動けないからだ。
定期的な交流の重要性
在宅の場合に必須となるのは、定期的な人との交流だ。その相手が、異変や緊急事態に気付けるからだ。
具体的には、
- 友人と定期的な交流がある
- 趣味のサークルで活動している
- 週一度のデイサービスに参加している
- 訪問医療や訪問介護を頼んでいる
- 離れて暮らす家族が一日一度電話をしてくる
- 公的な「見守り支援員」が定期的に訪問してくる(後述)
などの形で、本人を客観的な目で見られる第三者が周りに入っていればよい。こうすれば、体力的に生活が困難になった、物忘れが出てきた等があったとき、早い段階での発見や対応が可能になる。
定期的な交流は、安否確認としても機能する。たとえば、もしデイサービスを無断で欠席したら、施設の職員が電話をかけてくるだろう。ただ予定を忘れただけならそれでよいし、万が一のことがあってもまもなく発見されるので、問題に発展せずにすむ。
認知症をできるだけ早く発見すべき理由
「認知症と診断されるのが怖い」と言って検査を受けたがらない人は多い。だが、孤独死を防止するためには、すべきことは逆である。まだ元気なうちから積極的に医療機関を受診し、いち早く発見することがポイントになる。
というのも、認知症は、初期であれば健康な人とほとんど変わらない。本人にまだ十分な意思決定能力があるうちなら、
- 介護サービスの定期的な利用を始める
- 自分に合った老人ホームを探して入所する
- 法的手続きをすませておく、成年後見制度を開始しておく
など、症状が進行した後も生命を維持できる態勢を確保することができるからだ。
さらに、治療という面でも、発見は早ければ早いほど後は良い。認知症の原因は主に
- アルツハイマー型(=脳の記憶を司る海馬が萎縮する進行性の病気)
- 脳血管型(=小さな脳梗塞などにより脳が損傷する)
- レビー小体型(=脳の神経細胞にレビー小体と呼ばれるタンパク質のかたまりができる)
- 前頭側頭型(=脳の前頭葉と側頭葉前方が委縮する)
の4種類で、いずれも完全な治療法はまだないのだが、対応が早いほど進行を遅らせることはできる。脳血管性であれば、再発防止が悪化防止になる。
しかも、実は認知症には治る場合もあるということはご存じだろうか? 世間では「自分が誰かすら分からなくなってしまう」といった恐怖のイメージが独り歩きしているが、もし認知機能低下の原因が水頭症や、甲状腺機能低下症、ビタミンB12欠乏症などであれば、そちらを早めに治療すれば認知機能は完全に元通りになる。こう聞けば、受診をためらっていた人も検査を受けたくなるのではないだろうか。
高齢者施設にあらかじめ入居
社会からの孤立を防ぐには、高齢者が早いうちから高齢者施設へ入居するのも良い選択肢となる。介護スタッフや看護師、他の入居者などと常に交流がある環境に身を置いていれば、異変や緊急事態がすぐに発見されるからだ。
介護認定などの入居条件は施設によるが、比較的自立したうちから入れる施設もある。有料老人ホームでは、夫婦で入れる施設も多い。
各自治体の取り組み―見守り支援など
在宅の高齢者に対しては、各自治体が福祉の一環として孤独死防止の取り組みを行うようになった。職員やボランティアが定期訪問を行うサービスは、「見守り支援」「地域支援員」などの名称で多くの自治体が設けている。
他にも、
- 安否確認の定期電話サービス
- 地域で気軽に集まれる場を提供する
- 緊急通報装置を月額数百円など安価で貸し出す
- 郵便、新聞、電気、ガス、配達などの事業者と連携して、異変があった場合に連絡・支援につなげる
など、各自治体で様々なサービスが提供されている。こうしたサービスが利用されれば、緊急時に発見されない事態や、老老介護・認認介護の末に共倒れするリスクが解消される。
よく分からなければ地域包括支援センターへ
どうすればいいかよく分からない、という人もいるだろう。その場合は、とりあえず地域の「地域包括支援センター」に出向いてもらうのがよい。
地域包括支援センターとは、介護や高齢者福祉に関する相談を総合的に受け付けている「窓口」のような機関で、全国の自治体に設置されている。具体的には、利用できる公的制度や、地域にある介護施設・サービスなどを紹介している。次で述べるような見守り支援、緊急通報装置の貸し出しなども行っている。
高齢者支援の課題
以上のように、使える施設やサービス、医療は拡充されてきており、選択肢も増えている。本人の希望や条件によってこれらがうまく利用されれば、社会問題となるような孤独死は避けることができるだろう。
ただ、依然課題もあり、今後はさらなる対応が求められている。
認知症への誤解を解く
孤独死の大きな原因となっている認知症だが、上記の通り世間ではまだまだ誤解があるため、高齢者が早期発見や回復のチャンスをみすみす逃している。
なので、今後の方向性としては、認知症に関する正しい知識の普及が要されると思われる。
自治体の見守り支援で浮上している課題
異変に気付く人をもうけておくという点で、自治体による「見守り支援」は、高齢者の孤立防止に直結する取り組みとして評価できる。
だが、これにも一筋縄ではいかない面がある。地方の小さな町など、地域によっては、見守りや、そこで得た個人情報が、近所同士の監視や詮索、噂話に流用されるのではないかという懸念が浮上しているのだ。
かねてより、地域活動では、高齢のボランティア等が人権侵害行為を行ってしまい、行政上のトラブルに発展するケースが多発してきた。サービスの運用や支援員のなり手がどんな人かによっては、故意にせよ過失にせよ、見守り支援が「五人組」のように不適切に解釈されかねないのである。また、サービスが信用できないものであれば、利用も広がっていかないだろう。
公的な孤立防止の取り組みでは、ボランティアへの教育を徹底する、第三者への業務委託を行うなど、地域の実情に応じて本来の目的にかなった仕組みの構築が求められている。
高齢者が制度やサービスにアクセスできる環境
広く知られるべきことは他にもある。
前述の通り、各自治体には「相談窓口」として地域包括支援センターが作られているが、もしそれが知られていないならないのと同じだ。
デイサービスや見守り支援、高齢者施設なども同様で、せっかくサービスが存在していても利用されないなら効果は発揮されない。
高齢者が施設やサービスにかんたんにアクセスできるよう、まずは周知されるよう広報活動が求められる。
高齢者以外のケースでの対策と課題
では、高齢者でない、若者から中高年まで年代が孤立の果てに亡くなるケースはどうだろうか?
こちらは、雇用、経済的困窮、引きこもり、精神疾患など、原因のほうに対応することが結果として孤独死の対策、防止につながる。
社会の側では、各問題において、本人が一人で抱え込むことなく、支援とつながりやすくしていくことが課題となろう。公的制度の周知、医療情報の提供、相談しやすい機関づくりなど、あらゆる方面からの施策が講じられるべきである。原因の詳しい調査研究も要される。
社会から孤立して生命を維持できなくなることが戦後日本社会の病の一端である以上、その病巣深くにメスを入れることは必須である。問題をすぐに解決できるわけではないかもしれないが、部分的ではない広い視野で研究し、社会の意識に訴えていくことも必要だろう。
「戦前~高度経済成長」という社会問題
以上で述べてきた通り、社会問題となる孤独死の一部ケースは、戦前から高度成長の日本独特な精神風土が大きな原因の一つになっている。ここで、同じく戦後日本独特な引きこもりとは密接な関係が見えてくる。引きこもりを生んだ気質に加えて下記のジェンダー意識などもからみ合い、高齢世代を中心に、自分で自分の生命維持を不可能にしてしまうような性質が根差しているのだ。
以下では、現在高齢となっている世代が生きてきた戦前ファシズムから高度経済成長時代という歴史的・社会的背景にスポットを当てて論じようと思う。
なぜ孤独死は男性が8割を占めているのか?
孤独死は男性が圧倒的に多いことが指摘されている。
大阪府監察医事務所が「2017年大阪府監察医事務所取扱例のうち、死亡から発見まで4日以上経過した自宅死亡例」を対象に調査を行ったところ、一人暮らし1077人のうち871人、つまり約8割という圧倒多数が男性だった。同様の調査結果は他にも複数出ている。

なぜ男性に大きく偏っているのだろうか? そこには男性特有の原因があるはずだ。
「助けを求められない」ジェンダー意識
まず、介護などの現場では、男性には「周囲の助けを借りないのが強くて良いことである」というジェンダー意識があり、それが社会的孤立につながっているといわれている。体調不良や生活上の困難を抱えていても、周囲に口にしないのである。問題が手つかずのまま放置されれば、最終的には生命を維持できなくなる。
合理的に考えれば、公的サービスを利用したり、医療機関で検査を受けたりすることに「助けを求める」という言葉が充てられていること自体が的外れである。八百屋へ行って野菜を買うことを「八百屋に助けを求める」と表現するようなものだ。
しかしいくら合理的でないといっても、21世紀前半の日本には、そのような意識が頭に根差した男性が現に存在している。この意識は、他の社会問題と結びついて、さらに深化していく。
軍国主義下で育った生い立ち
次に、これは女性と共通だが、現在の80代以降は戦争経験世代とイコールでつながる。したがって、その生い立ちがどのようなものかといえば、彼らは軍国主義熱が燃え盛る社会で育ち、学校では「お国のために鬼畜米英と戦って死ぬ」よう教わっていた。この世代は、若いころに自分の人生を考え、先のビジョンを持つということがなかったのである。
また当時は、日本軍はアメリカ相手に連戦連勝だと、事実とはまるで異なる話が当たり前に信じられていた。「大和魂があれば竹やりでB-29を落とせる」といった非合理的な精神論も平然と闊歩していた。軍指導部が「できたらいいのに」という希望と実際にできることを混同していたことは、無謀な突撃で案の定大量の死者を出したインパール作戦に代表される。子どもというのは周囲の大人をまねすることで成長していくものだが、いまの80代以降が見本としたのはこのような大人たちだったのである。情報の真偽を自分で確かめるとか、合理的な予測に基づいて計画を立てるという習慣は学んでいない。
戦争経験世代は、現実を生きていく術を教わっていないのである。
定年退職でぼう然自失となる“サラリーマン”
このように、国家にすべてをささげるよう教育、統制されていた日本人は、ファシズム体制が崩壊するとぼう然自失となった。恐怖から解放され、教科書に墨を塗ったはいいが、ではどう生きればいいかは分からなかったのである。戦後、人々はこの頭の空洞を「会社への没入」によってしのごうとする。
高度成長時代の“サラリーマン”男性は、会社名とそこでの肩書きがアイデンティティのすべてになっていた。戦前ファシズムに代わり、今度は自己のすべてを会社にささげたのである。そのため、“サラリーマン”が”サラリーマン”でない自己を規定できず、定年退職したとたんぼう然自失となることは、これまでも様々な分野から指摘されてきた。
“サラリーマン”以外のことができない帰結
戦後のこうした状況から、日本社会には「”サラリーマン”以外にできることがない人」が大量に生み出された。
定年退職で自己を見失う男性は、会社以外の場で人間関係を築いたり、社会とつながったりすることを苦手としている。近所付き合いが希薄だったり、地域や介護のコミュニティに参加しないことが社会的孤立を引き起こし、最終的には孤独死につながっていくのである。
また、すでに述べたジェンダー意識により、高齢男性には自分が家事をすることを格好悪いとみなす人が多い。そもそも家事ができないこともめずらしくない。そのため、妻に先立たれた後、自力では食事や身の回りのことが十分できず、低栄養や不衛生に陥った結果として孤独死することも指摘されている。
「ミニ・インパール作戦」―合理的思考を学べなかった時代の負の遺産
以上のようにして生命維持不能へと歩を進めてしまう高齢男性だが、合理的に考えれば、そのままでは生きられなくなることは最初から明白だ。
妻や子がいるというだけで老後に漠然とした安心感を抱く男性がいるといわれる。しかし、「妻のほうが長生きする」という無言の前提には根拠がない。それに、たとえ妻が存命はしていても、ガンで入院した、介護施設へ入所したなどにより、共同生活が終わることは十分あり得る。また、子にも人生があるので、遠方で暮らす可能性は高いだろう。そうして一人暮らしになった時に、食事をはじめ身の回りのことをどうやればいいか分からないのであれば、生命を維持できなくなることは合理的に予測できるはずだ。とりわけ認知症について言うならば、自分がそれにならない保証はどこにもない。
ところが、社会から孤立する高齢男性は、こうした合理的予測をしていない。何の根拠もなく、何とかなるんだとか、自分は認知症になどならないなどと信じて猛進し、案の定破滅するのである。この成り行きと結果には既視感がある。太平洋戦争最悪の失敗、インパール作戦と重なると筆者には思われるのである。
大日本帝国体制は崩壊したが、戦後の企業群は無数のミニ・大日本帝国だった、とよくいわれる。ならば合理的思考の欠如を原因とする高齢男性の孤独死は、インパール作戦の一人版ミニチュアなのだと言うことができるだろう。戦前ファシズムと正面から向き合えず、克服することができなかった戦後日本人の性質が、70年の時を経て徴表した形の一つといえる。
「引きこもりの別形態」―戦後の日本人全体が抱える病
一般に、引きこもりとは自宅・自室から出られない人のことを指している。世間では、その人が個人的に問題を抱えているという認識が、まだかなり浸透しているように思う。
しかしもっと本質的な部分に目を向ければ、社会と適切につながることができず、自己や狭い世界に閉じこもる気質自体は、戦後の日本人全体に共通している。元”サラリーマン”が会社での上下関係なしに人間関係を築けないのはその一端だ。外形的にはグローバル企業である東芝で不正会計事件が起こった際には、経営幹部らの極度に閉鎖的な体質が原因として指摘された。一見普通に外を歩き、会社で働いている人々が、本質的・心理的には引きこもっており、深く孤立しているのである。戦後の日本という時と場所に特有な、病的な気質である。
老夫婦の介護に関しては、介護が家庭に閉じこもって行われがちなことが前々から問題視されてきた。負担が重くて背負いきれないにもかかわらず、社会に存在している介護サービスや公的支援とつながっていこうとしないで、家の中に閉じこもるのである。
介護で家に引きこもる傾向も、とりわけ妻を介護する夫に強いといわれる。妻への虐待や介護殺人、心中などの温床となっている。
こうした社会と適切につながれないゆえの孤独死もまた、戦後の日本人に共通する引きこもり気質の表れ方の一つだと位置付けられるだろう。
高齢世代本人が自分の意識を変えること
以上の通り、孤独死の一部ケースの背景には、ジェンダー意識や戦前・戦後の日本人の特殊な精神があるといえる。
いくら適切な制度、情報豊富な窓口、すばらしい医療、生きる喜びを感じられる介護サービスが存在していようとも、上記のような意識から高齢者本人が拒絶するのであれば、孤独死は誰にも防止しようがない。
したがって、こうしたケースでは、本人がいかに自分の意識を変えられるかが対策のポイントになる。
おわりに―孤立しないことは生きるためのスキル
自己の殻に閉じこもって問題を悪化させてしまいがちな傾向は、若い世代とて例外ではない。こう聞いたらゾッとするかもしれないが、現代の人々は、自覚している以上に、戦前ファシズムから戦後昭和の歪んだものの見方や人生観から強い影響を受けている。
一例だが、留学の場面では、「日本人留学生には困ったことがあっても周囲に言わない癖がある」というのが定説化している。学校生活で足りないものがあったり、体調がすぐれなかったりしても一人で悶々としているうちに状況が悪化し、後でホストファミリーや学校から「なんでこんなになるまで黙ってたの?」と驚かれる、というのだ。海外現地の留学センターでは、日本人特有の行動「enryo(=遠慮)」として知られていることもある。誰かとつながっていればかんたんに解消できたはずのことが、黙っていたせいで、かえって自他ともに困るような大きなトラブルに発展してしまうのである。
だから留学前の講習やパンフレットでは、しばしば「困ったことがあったらはっきり言うように」と注意がある。困っていることや自分がどうしたいのかを早めに人に伝え、もしうまく伝えられない場合は、誰かが適切なところにつないでくれるまでがむしゃらに「困っている」と発信し続けるように、という。学校の窓口や留学生のグループで積極的に情報交換することは、現地で流行っている詐欺に気付くなど、防犯にも役立つという。
自分を孤立させないことは、生きていくための基本的なスキルなのである。

その基本的スキルが普及せず、人が生命を維持できなくなってそのまま亡くなってしまう孤独死は、日本社会の様々な要因から生じた特異かつ痛ましい問題といえよう。
関連記事・参考リンク
著者・日夏梢プロフィール||X(旧Twitter)|Mastodon|YouTube|OFUSE
中年の引きこもりと仕事のジレンマ&今後のライフスタイル – 自宅・自室から出られない人だけでなく、管理職や経営者の閉鎖性や、人々の政治に関わりたがらない性質などを含めて「引きこもり体質」を論じた。
『千と千尋の神隠し』考察と論評―両親、坊、湯屋が表象した戦後日本 – アニメ映画の巨匠・宮崎駿監督の代表作は、高度経済成長以後、特にバブル期の日本人を描いた作品である。引きこもりも中心的なテーマとして扱われている。
日本の企業文化「井の中の蛙」―その特徴と変革への指針7選 – 日本企業の特殊性を指摘した。
戦争体験談は現在、風化どころか不足中―各世代への提言 – 戦前ファシズム、特に一般人のそれの検証が不十分であると訴えた。
『最高の人生の見つけ方』あらすじ解説と感想―生き方を論ずること – 昭和世代の男性に熱狂的ファン層を抱える女優・吉永小百合が主演した日本でのリメイクにあたって、制作者がシニア層男女数千人に「人生で死ぬまでにやりたいことは何か」についてリサーチを行ったところ、話になるようなアイデアは出てこなかったという。示唆に富むと思われる。
【参考資料】
老老介護・認認介護とは?離れて暮らす両親にできること – みんなの介護
他、本文中外部リンク